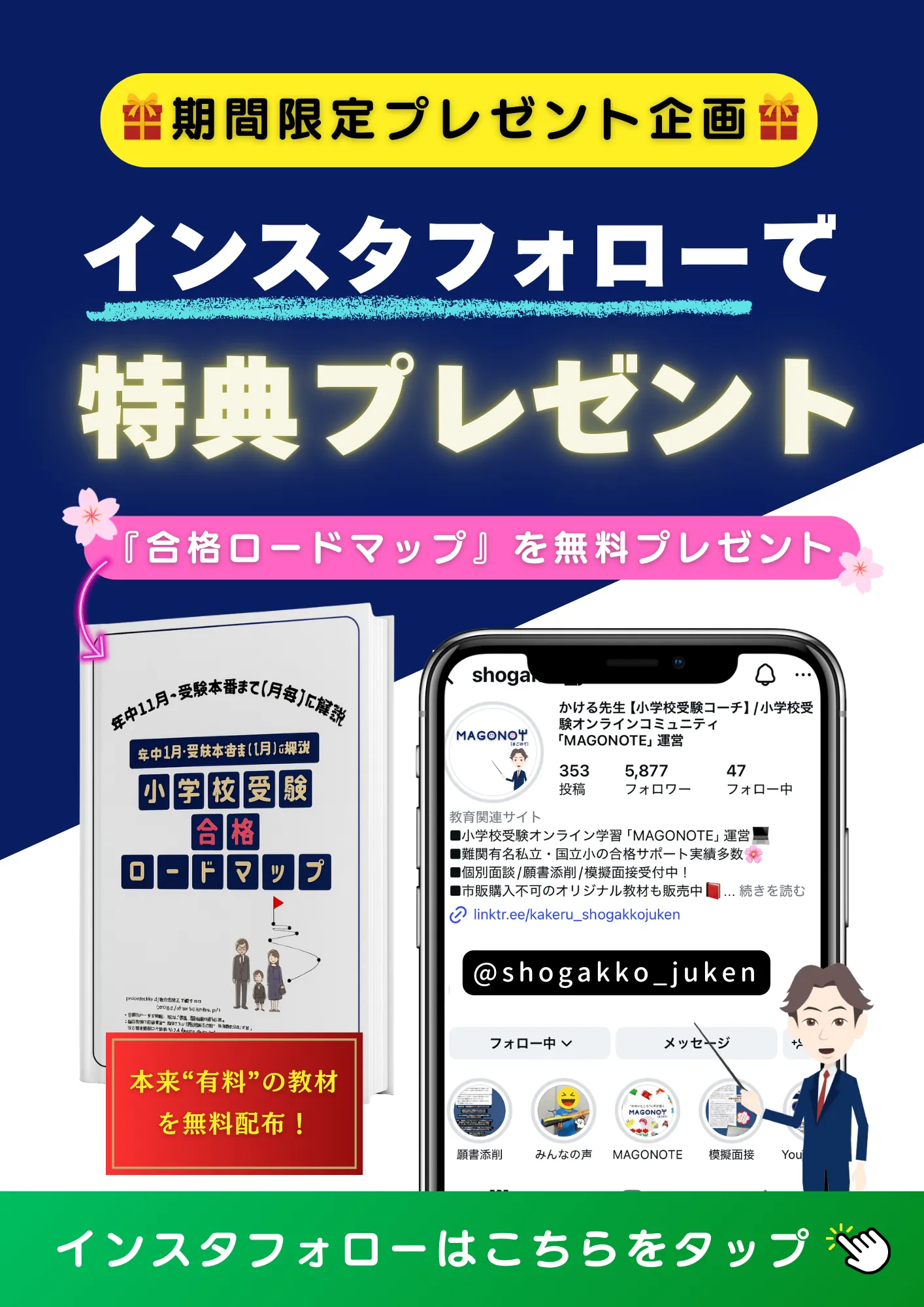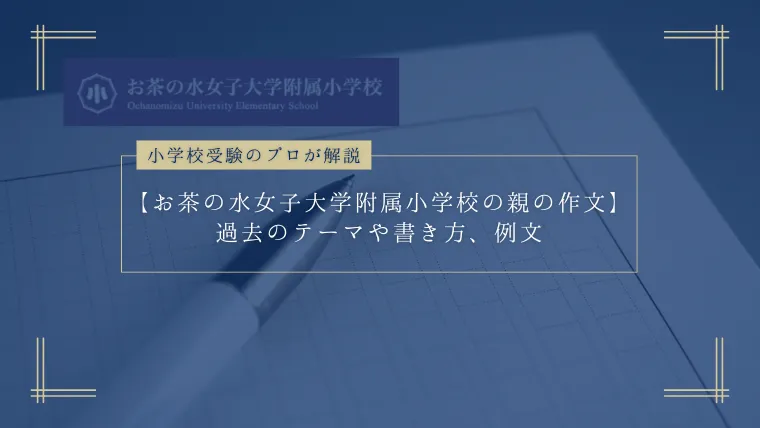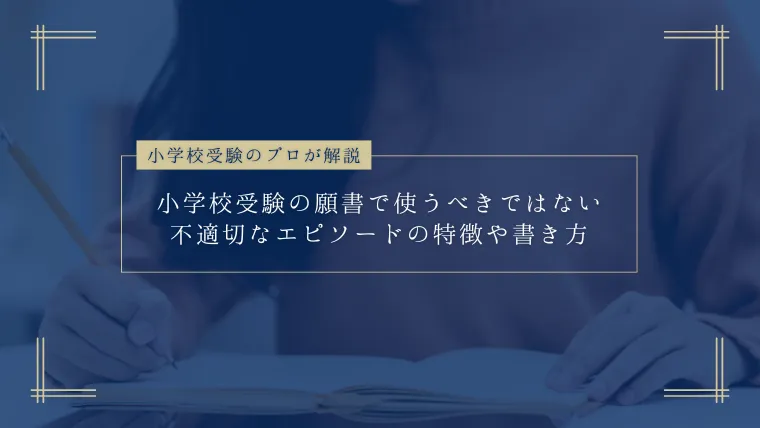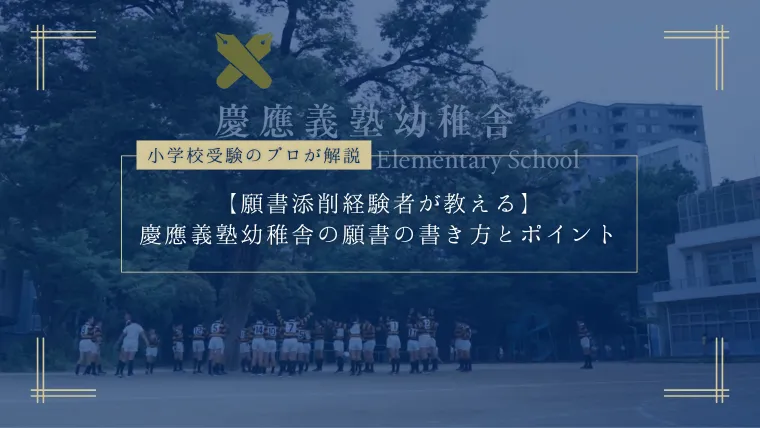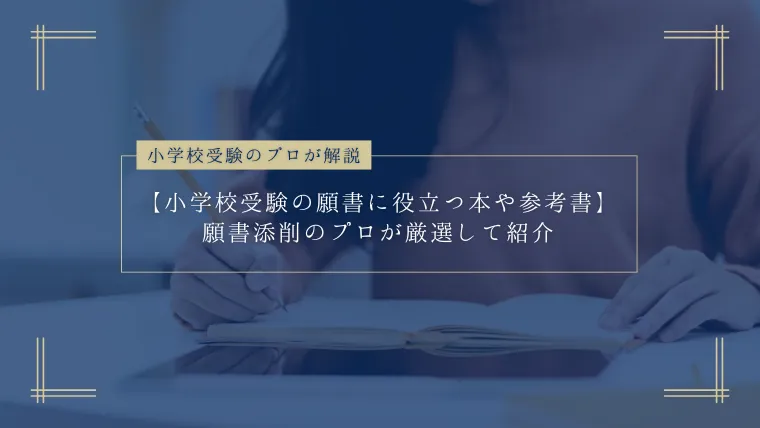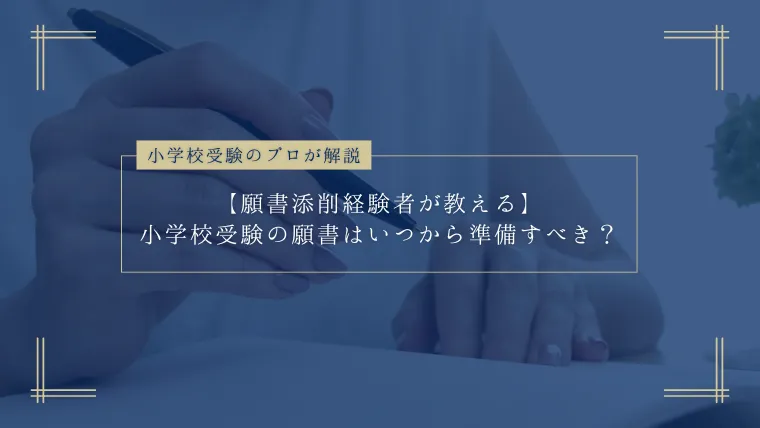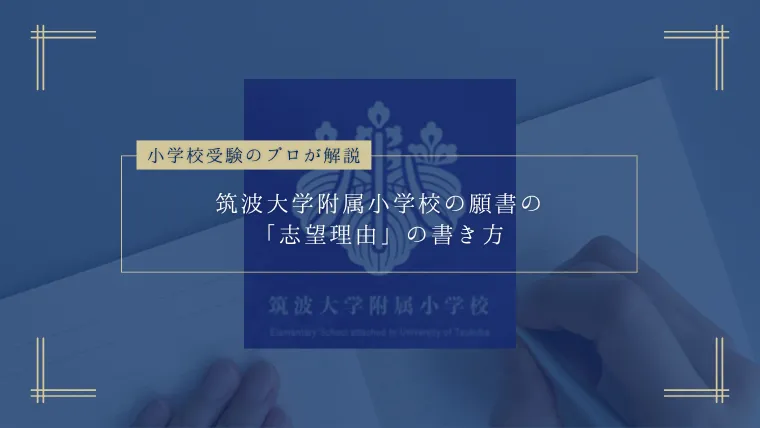慶應横浜初等部の願書の書き方とポイント【願書添削のプロが解説】
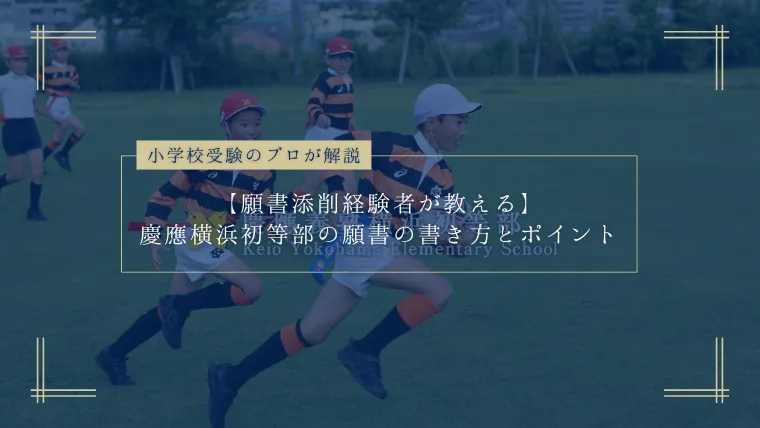
こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。
今回は慶應義塾横浜初等部の願書の書き方やポイントについて、願書添削の経験を踏まえて詳しく解説していきますね!
慶應横浜初等部の願書を書く際には、非常に重要なポイントがいくつかあります。
1つ目は、横浜初等部よりも長い歴史を持つ慶應義塾における一貫教育の源流「慶應幼稚舎」との違いをきちんと理解すること。
2つ目は、慶應横浜初等部ならではの教育理念を正しく理解し、それを示すこと。
そして、3つ目は、『福翁自伝』や『福翁百話』などの課題図書を読んだうえで、ご自身の家庭の教育方針に福澤諭吉先生の思想を反映させることです。
今回は、このようなポイントを踏まえたうえで、慶應横浜初等部の願書の書き方やポイントについて、今までの添削経験を踏まえて詳しく解説していきます。
13,000字超のボリューミーな内容になっているので、横浜初等部を受験する方は必ずブックマークをして何度も見返せるようにしておきましょう!
慶應横浜初等部は、数ある私立小学校の中でも「最も願書を重要視している学校」と言われています。
その理由は、他の学校が実施している親子面接や保護者面接がないためです。
多くの私立小学校では、面接を通じてご家庭の教育方針や雰囲気、ご両親の人柄などを確認します。
また、保護者がどのような教育観を持ち、日々どのように子育てに取り組んでいるのかを知る貴重な機会となります。
ですが、横浜初等部では面接が一切ないため、“願書を通して”ご家庭の教育方針やお子さまとの普段の関わり方などをチェックしているのです。
そして、願書の内容がそのまま、ご家庭の教育観やお子さまに対する思いを示すものとなり、それが受験の成否に大きく影響を与えることになります。
そのため、「慶應横浜初等部の願書=学校側に自分たちの教育方針をしっかりと伝える重要な手段」という意識を持つことがまずは大切です。
さらに、横浜初等部は、願書の記入欄が他の学校に比べて大きく、『福翁自伝』や『福翁百話』といった課題図書があることからも、願書の重要性がより一層強調されていることが分かります。
課題図書に関しては、福澤諭吉先生の思想を正しく理解し、それを家庭内でどのように実践しているかを具体的に示すことがポイントです。
また、課題図書がある分、当然願書を完成させるには時間がかかります。
実際に、合格した家庭の多くは、この願書作成にかなりの時間と努力を費やしています。
そのため、慶應横浜初等部の願書を仕上げるには、少なくとも数週間から数ヶ月の準備が必要であり、早めに取り掛かることが成功の鍵になることを覚えておきましょう。
次に、慶應横浜初等部の願書で具体的にどんな内容を記入しなければならないのかについて、詳しく解説していきます。
慶應横浜初等部の願書を書く際は、特に「お題」をきちんと読み解くことが非常に大切です。
お題を正しくを理解することで、横浜初等部の意図に沿った内容の願書を書くことができます。
逆に、テーマをうまく理解できていない状態で文章を考えると、結果的にズレた内容の願書になってしまい、先生方にご家庭の魅力を伝えることができません。
そこで今回は、慶應横浜初等部の願書の2つのお題と、それらをどのように読み解けばよいのかについて詳しく解説します。
慶應横浜初等部の願書を一緒に紐解いていきましょう。
慶應横浜初等部の願書の最初のお題は「志望理由」です。
ただし、「志願者の様子や家庭の教育方針に言及しながら本校の特にどの点に共感して志望したのか書いてください」という条件があるため、これらをきちんと守った上で書く必要があります。
まず、条件1の「志願者の様子や家庭の教育方針に言及しながら」という点から深掘りしていきましょう。
「志願者の様子」はお子の性格や特質(長所短所)を、「家庭の教育方針」はお子さまを育てるにあたって親御さまが大切にしていることを指します。
そのため、願書を書き始める前にまずはご家庭で大切にされてきたことをご夫婦で話し合い明確にしましょう。
そして、子どもの特質や長所が伝わるようなエピソードも探し、文章にうまく盛り込むことが大切です。
エピソードの見つけ方や選び方に関しては以下の記事で例を踏まえて解説しているので、こちらもチェックしてみてくださいね。
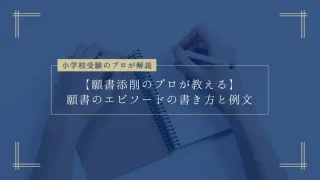
「本校の特にどの点に共感して志望したのか書いてください」という2つ目の条件に関しては、横浜初等部に対して魅力を感じる点を具体的に記述することがポイントです。
そのためには、慶應横浜初等部のならではの教育目標やカリキュラムを事前に理解しておく必要があります。
また、横浜初等部への理解を深めることは、条件1の「志願者の様子」や「家庭の教育方針」においてどんな内容を書くか決定するうえでも重要になります。
そのため、横浜初等部のHPやパンフレットを見て終わりではなく、説明会や関連書籍、在校生の声を踏まえて徹底的にリサーチするようにしましょう。
ちなみに、慶應幼稚舎と横浜初等部の両方を受験される方の中には、学校名だけと表面的な教育目標の部分だけ書き換えて、中身はほぼ同じものを使い回す方もいますが、これを行うと一発OUTです。
なぜなら、横浜初等部と幼稚舎は、慶應義塾一貫教育の源流という点、福澤先生の「独立自尊」をはじめとした思想や精神を大切にしている点では同じと言えるかもしれませんが、それを達成するための手段(教育目標やカリキュラム)はまったく異なるからです。
(そういった意味では、幼稚舎と横浜初等部はまったく違う学校と言っても過言ではないでしょう。)
具体的にどのような点において違いがあるかは後述しますが、「使い回しができる学校ではない」ということは頭に入れておきましょう。
志望理由の具体的な書き方については、以下の記事でも詳しく解説しているので、こちらも後ほどチェックしてみてくださいね!
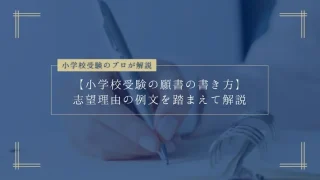
横浜初等部の願書の2つ目のお題は、「『福翁自伝』を読み、どこに共感したのか、その理由と、それを本校の入学以降、具体的にどう活かしたいのか書いてください」というものです。
ただし、課題図書は受ける年度によって異なることがあるので注意しましょう。
ここで、これまでの横浜初等部の課題図書の変遷を見ていきましょう。
【過去のお題の変遷】
■2013〜2018年度入試
課題図書: 『福翁自伝』
お題:「お子様を育てるにあたって『福翁自伝』を読んで感じるところを書いてください」
■2019年度入試
課題図書: 『伝記 小泉信三』(慶應義塾大学出版会)
お題:「『伝記 小泉信三』を読んで、慶應義塾の校風・雰囲気について感じるところを書いてください」
■2020年度入試〜2022年度入試
課題図書:『福翁百話』
お題:「『福翁百話』の家庭や親子関係に関する部分を読んで、保護者と志願者の関わりについて感じるところを書いてください」
■2023年度入試
課題図書:『福翁百話』
お題:「『福翁百話』を読んで、最も共感した部分を、具体的なエピソードを交えて書いてください」
■2024年度入試
課題図書: 『福翁自伝』
お題: 「『福翁自伝』を読んで最も共感した部分とその理由、またそれを志願者の慶應横浜初等部入学以降、どのように活かしたいかを書いてください」
■2025年度入試
課題図書: 『福翁自伝』
お題: 「『福翁自伝』を読んで最も共感した部分とその理由、またそれを志願者の慶應横浜初等部入学以降、どのように活かしたいかを書いてください」
このように2020年度入試以降はずっと『福翁百話』だったのですが、2025年度入試では『福翁自伝』に回帰して、大きな混乱を招きました。
そのため、慶應を受験するのであれば、『福翁自伝』と『福翁百話』の2冊はマストと言えるでしょう。
また、「『福翁自伝』を読み、どこに共感したのか、その理由と、それを本校の入学以降、具体的にどう活かしたいのか書いてください」というお題を読み解くと、主に2つの条件があることがわかります。
1つ目は、「どこに共感したのか、その理由」です。
そして、2つ目は「それを志願者(お子様ご本人)の入学以降、具体的にどう活かしたいのか」です。
この2つの条件は独立したものではなく、むしろ密接に関係するので、2つ目の条件を見据えて、課題図書の中からどの部分を使うか決めることが重要です。
*条件1は親御さま(保護者)が主語、条件2はお子さまご本人が主語となっています。
そのため、早い時期から2冊をしっかりと読み、共感する部分をいくつかピックアップしたうえで、入学後にどのように活かしたいのか、複数のパターンを作っておくことをおすすめします。
このお題は初めて慶應の願書を書く方にとっては難しいと思うので、自信がない方は添削経験のある方に協力してもらうことをおすすめします。
横浜初等部の願書を書くときのポイントを一言でまとめると、「横浜初等部ならではの教育目標や価値観を理解すること」です。
そのためには、慶應義塾における一貫教育の源流として長い歴史を持つ慶應幼稚舎との違いをしっかりと理解する必要があります。
つまり、幼稚舎との違いを通して、横浜初等部ではどのような教育目標のもと、どんな授業や行事を行っているかも知ることが重要なのです。
そうすることで初めて、横浜の願書を書く際にどんな教育方針で、どんなエピソードを交えてかけばよいのか見えてくるはずです。
そこで以下では、横浜初等部の願書を書くうえで必ず知っておくべき特徴について、幼稚舎と比較しながら丁寧に解説します。
慶應横浜初等部の学校分析を進めている方は、復習もかねて読み進めてくださいね。
横浜初等部は、幼稚舎と違って原則2年ごとにクラス替えが行われます。
慶應幼稚舎では「6年間担任持ち上がり制」が長年採用されていますが、これにはきめ細かい指導ができるというメリットがある反面、担任の先生やクラスの生徒と相性が合わない場合でも「逃げ場がない」というデメリットがあります。
実際、慶應幼稚舎ではこの制度が原因で過去に悲しい事件も起きています。
その点、横浜初等部では、3年生と5年生時にクラス替えが行われます。
また、慶應横浜初等部では学力向上のために教科担任制を導入しているのも魅力のひとつです。
教科担任制は、専門の教員が科目ごとに授業を担当する方式で、一般的には中学や高校で採用されるケースが多いですが、横浜初等部ではこれを3年生から実施しています。
教科担任制は幼稚舎も導入していますが、横浜初等部と幼稚舎では担任が受け持つ範囲が異なります。
幼稚舎の担任は国・社・算・総合(生活)と体育の一部を受け持っていますが、横浜初等部の場合、3年生以降は担任の専門科目以外はすべて専科教員が授業を担当します。
つまり、より専門性の高い授業を受けることができるということです。
また、幼稚舎と違って、横浜初等部の1次でペーパーテストが実施されるのは、このようなレベルの高い授業についていける素地やポテンシャルがあるかどうかを判断するためとも言われています。
このようなことからも横浜初等部では、小学生のうちから高い学力を身につけさせることを重視していることがわかる思います。
先ほどもお伝えしたように、慶應横浜初等部では基礎学力の向上を重視しています。
幼稚舎は、福澤先生の「先ず獣身を成して後に人心を養え」という考えに沿って、小学校生活では勉強よりも体力をつけることを重視した教育方針を採用しています。
また、普段の生活でも比較的子どもたちの自由度が高い学級運営をしており、クラスによっては漫画やゲームもOKです。
一方で、横浜初等部では低学年のうちにから「しっかり勉強する」という習慣を大事にしているため、一般的な公立小学校の低学年より勉強量は多くなっています。
幼稚舎ではOKなゲーム・漫画は一切禁止。そのかわり図書館などで本を借りる子も多いようです。
また、横浜初等部が幼稚舎より学力を重視していることは、試験内容の違いを比較してみてもわかると思います。
横浜初等部は幼稚舎の試験と違って、1次試験と2次試験の2段階選抜方式で実施されています。
最大の特徴は1次試験でペーパーテストが行われること。
ペーパーテストの内容は、数量や図形、お話の記憶、言語などの分野から出題されることが多く、先ほどお伝えしたように「専科」の授業についていける土台が作られているかをチェックされています。
また、1次試験を突破できたら、今度は2次試験で、集団テスト(絵画・制作・行動観察)運動テストが行われます。
これは幼稚舎に近い内容となっており、その子の社会性や協調生、 コミュニケーション能力のほか、発想力や独創性などもチェックされています。
このように、横浜初等部では多角的な試験を通して評価しているため、幼稚舎よりも偏差値的な評価が強いと言われています。
ですので、どの分野でもしっかりと高得点を取れるような実力をきちんと身につける必要があるのです。
このようなことからも、横浜初等部が幼稚舎に比べて「実力主義」と言われている理由がお分かりいただけると思います。
慶應横浜初等部では、入学時の教育目標として「律儀正直親切」を掲げ、卒業するときには「身体健康精神活発」「敢為活発堅忍不屈の精神」の基礎を身につけることを目標にしています。
それぞれの言葉を簡単に解説すると以下のようになります。
「身体健康精神活発」
→体も心も健康で元気に過ごす
身体健康: 子どもたちが十分に運動し、バランスの良い食事をとり、健康的な生活習慣を大切にすること。
精神活発:心が明るく、前向きで、好奇心旺盛であること。新しいことに挑戦する意欲や、自分の考えをしっかり持ちながらも他人と協力する姿勢を指します。
「敢為活発堅忍不屈(かんいかっぱつけんにんふくつ)の精神」
→困難に立ち向かい、最後まで諦めずに頑張る心
敢為:困難なことでも勇気を持って挑戦すること。
活発: 生き生きと積極的に行動すること。
堅忍:辛い状況でも耐え抜く強い心。
不屈:失敗や困難があっても挫けず、諦めない心。
また、これらの基礎を培うために、「体験教育」「自己挑戦教育」「言葉の力の教育」を3つの柱として日々の授業や学校行事を行っています。
この3つの柱に関しては横浜初等部のHPでも詳しく解説していますが、ここでも簡単にまとめておくので参考にしてみてください。
■体験教育
授業や課外活動を通じて、観察や体験を大切にし、抽象的な概念や理屈を実感を伴って理解する力を育てます。子どもたちが日常的な生活や遊びの体験が乏しくなっている現状を踏まえ、非日常的な体験だけでなく、日常生活と結びついた体験や創造的な遊びを豊かにすることの重要性が強調されています。これにより、物事の本質を見抜く洞察力が培われます。
■自己挑戦教育
得意分野で高い目標に挑戦することや、苦手なことに積極的に取り組み少しずつ克服していく体験を大切にします。例えば、運動を通じて得た自信を他の分野にも広げることで、困難に直面しても諦めず、粘り強く取り組む力を育てます。こうした経験の積み重ねが、「自分にはやり遂げる力がある」という自負心と強い意志を生み出し、将来、先導者となるための基礎を築きます。
■言葉の力の教育
読書や表現の訓練を通じて、読む力、書く力、聞く力、話す力をバランスよく育てます。これらの力は、学力や論理的思考力の基盤であり、他者と協力する力の基礎でもあります。また、言葉の力をさらに発展させ、現象を理解し、問題を発見し解決する力につなげるため、数や量を扱う力、いわば「科学の言葉」の基礎も重視しています。このように、幅広い言葉の力を養うことで、思考力や問題解決力の成長を目指します。
このような教育目標から、横浜初等部は幼稚舎の華美なイメージとは違って、地に足のついた考えを持っていることがわかると思います。
派手な見た目より、中身を重視するという考えは、早稲田実業学校初等部の校是は「去華就実」とも少し重なる部分があると個人的には思います。
そのため、横浜初等部を受験するのであれば、このような教育目標や考えを正確に理解したうえで、日々の生活を丁寧に過ごすことがポイントになります。
また、願書を通して、上記の教育目標と同じ方向の考えを持っていること、また、そのために具体的に子どもとどう接してきたのかなどを、エピソードを踏まえて書くことが重要です。
このことからも、幼稚舎の願書を横浜初等部にも使い回すのがNGであるとわかっていただけると思います。
慶應幼稚舎にはない横浜初等部ならではの科目として「福澤先生の時間」があります。
「福澤先生の時間」は、1年生〜6年生まで毎週1時間の授業が組まれており、低学年では福澤諭吉先生が著した子ども向けの本「ひびのおしえ」を読んだり、生涯のお話を聞いたりします。
ちなみに、授業の進め方については紙に「原文」と「現代語訳」を書かせるクラスもあれば、単に内容を説明するだけのクラスもあります。
そして、高学年になると福澤先生やその門下生たちが日本の近代化において果たした役割や慶應義塾の歴史について学ぶようになります。
こうした授業を通して、慶應義塾の歴史やその創立者である福澤先生のスピリッツを学び、身につけていくことを大切にしています。
このような背景を踏まえると、願書の課題図書である『福翁自伝』や『福翁百話』を親御さん自身が読み、福澤先生に対する理解を深めることの重要性もご理解いただけると思います。
横浜初等部の願書では、これらの著書の内容を絡ませて書かなければならないため、流し読みするのではなく、メモを取りながら熟読するようにしましょう。
先ほどお伝えしたように、どちらが課題図書になるかはその年になるまでわからないため、時間があるうちにしっかりと読んでおくことをおすすめします。
慶應横浜初等部といえば、充実した教育設備・環境も大きな魅力の一つとされています。
横浜初等部の敷地面積は、幼稚舎が2.1万㎡なのに対して3.8㎡とかなり広くなっています。
また、渋谷から江田駅まで30分強と、都心からのアクセスも幼稚舎には敵いませんが、悪くはありません。
さらに、天然芝のグラウンドに、さまざまな生き物が生息するビオドープもあり、先ほどご紹介した横浜初等部の三本柱のひとつである「体験教育」にもぴったりの教育環境となっています。
このような教育設備を維持するためには「施設設備費」がより多くかかるため、横浜初等部の学費は高いと言われています。
ですが、学費を差し引いてもこのような設備や環境に魅力を感じる保護者は多いです。
実際、添削をしていると、横浜初等部の自然豊かな環境に対して魅力を感じていることを記述される方も多いです。
そのため、お子さまが生き物や植物好きだったり、自然の中での体験を大切にしてされてきたなら、そのエピソードと絡めながらこのような点に触れるのも選択肢のひとつだと思います。
願書の下書きを考え始める前に、ブランド力や知名度だけでなく、横浜初等部のどんな点に魅力を感じるのか、具体的に書き出してみることも大切です。
慶應横浜初等部の願書を書くための手順は、以下の通りです。
1.自己分析・学校分析をする
2.願書の基本的な文章の型を学ぶ
3.文章の骨組みを作る
4.願書の下書きを作成する
5.プロの添削を受ける
初めて小学校受験に挑戦される方は、つい「とにかく早く願書を完成させなくては!」という焦りから、いきなり「4.願書の下書きを作成する」というステップから始めてしまうことが多いです。
ただ、自己分析や学校分析を十分に行わずにいきなり文章を書き始めると、文章全体に一貫性がなく、言いたいことがバラバラになってしまい、「支離滅裂な願書」になりやすいです。
また、横浜初等部のHPやパンフレットに載っているキーワードを無理やり繋げて使った「継ぎ接ぎ願書」になることも少なくありません。
これでは、読み手である学校側にご家庭の本当の考えや子どもの魅力が伝わらず、願書の意図をしっかり汲んでもらえない可能性が高くなります。
また、このように準備不足で書かれた文章は、添削の段階で内容そのものを大幅に修正する必要が出てくるため、結果的に二度手間になり、時間も労力も余計にかかるという悪循環に陥ってしまいます。
そうならないためには、まず「願書作成の土台」となる自己分析や学校分析をしっかりと行うことが重要です。
これらを丁寧に進めることで、自分たちの思いや子どもの個性を自然に文章に落とし込むことができ、願書全体に一貫性が生まれます。
また、自己分析と学校分析をきちんと行うことで、横浜初等部が重視している教育方針との方向性が一致する内容を自然に盛り込めるため、読み手にしっかり伝わる願書を書くことができます、
願書作成は、焦らず順序を守ることが成功のカギなので、先ほどご紹介した「5つのステップ」を丁寧に進めていくことが、効率的かつ効果的に質の高い願書を作成するための近道です。
各ステップで具体的に何をすれば良いのか、どのように進めれば良いかについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
約20,000字超のボリューミーな内容になっています!
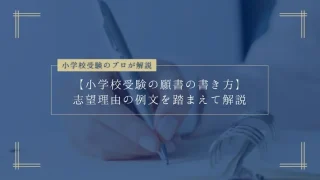
かけるの願書作成・添削講座

今回は、慶應横浜初等部の願書の書き方やポイント、注意点などについて、詳しく解説してきました。
ですが、ここまでを読んだうえで、
「自分1人で願書を書き上げられる自信がない…」
「願書作成をサポートしてほしい」
「自分の下書きに自信を持てないから添削を受けたい」
というような不安やお悩みを抱えている方も多いと思います。
そのお気持ち、とてもわかります。
特に、慶應横浜初等部の願書はかなり難しいと言われています。
なぜなら、テーマも抽象的で、課題図書もあり、記入欄も大きいからです。
そのため、どんな要素を盛り込むか明確にした後で、しっかりと文章を構成していく必要があります、
それに、願書の作成手順や書き方がわかっていても、育児やお仕事で忙しかったり、文章力に自信がないと、自分1人で取り組むのは難しいですよね。
そのような方は、私の「願書作成・添削講座」もご検討ください。
私が伴走者として願書作成をサポートいたします。
私の願書作成・添削講座では、自己分析のお手伝いから文章の書き方、添削まで手厚くサポートさせていただいております。
また、ご家庭のニーズに合わせて3つのプランをご用意しているため、ご自身のスタイルやご要望に合ったサービスを選ぶことができるのも魅力のひとつです。
お一人で願書を書く自信がない方、早めに願書の準備を始めたい方は、以下のボタンから私の願書作成・添削講座の詳細もチェックしてみてくださいね!
過去の添削例などを確認したい方は以下のページに載せているので、ぜひ確認してみてくださいね!
今回は慶應横浜初等部の願書の書き方やポイント、注意点などについて、幼稚舎との違いも踏まえて詳しく解説してきました。
慶應幼稚舎と同様、横浜初等部の願書もしっかりと書こうとすると、かなり時間がかかります。
また、先生方の印象に残る願書を書くためには、課題図書以外の福澤諭吉先生の著作を読んだり、慶應義塾や横浜初等部の歴史をきちんと知ることも必要不可欠です。
そのため、慶應横浜初等部の方は、今日から願書に向けて準備を始めましょう。
具体的に何から始めればいいかわからない方は、以下の記事や私の願書作成添削講座も参考にしてくださいね。
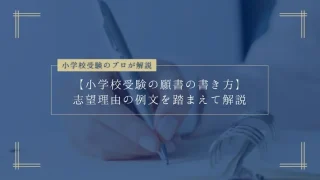
小学校受験の現役講師兼コーチである私が運営している小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」では、願書作成の他に受験対策や面接対策にも役立つコンテンツが多数あるため、こちらもぜひチェックしてみてくださいね!
![小学校受験SPOT[スポット]](https://resigrit.co.jp/shogakko-juken_spot/wp-content/uploads/2024/02/shogakko-juken_spot_logo_blue.webp)