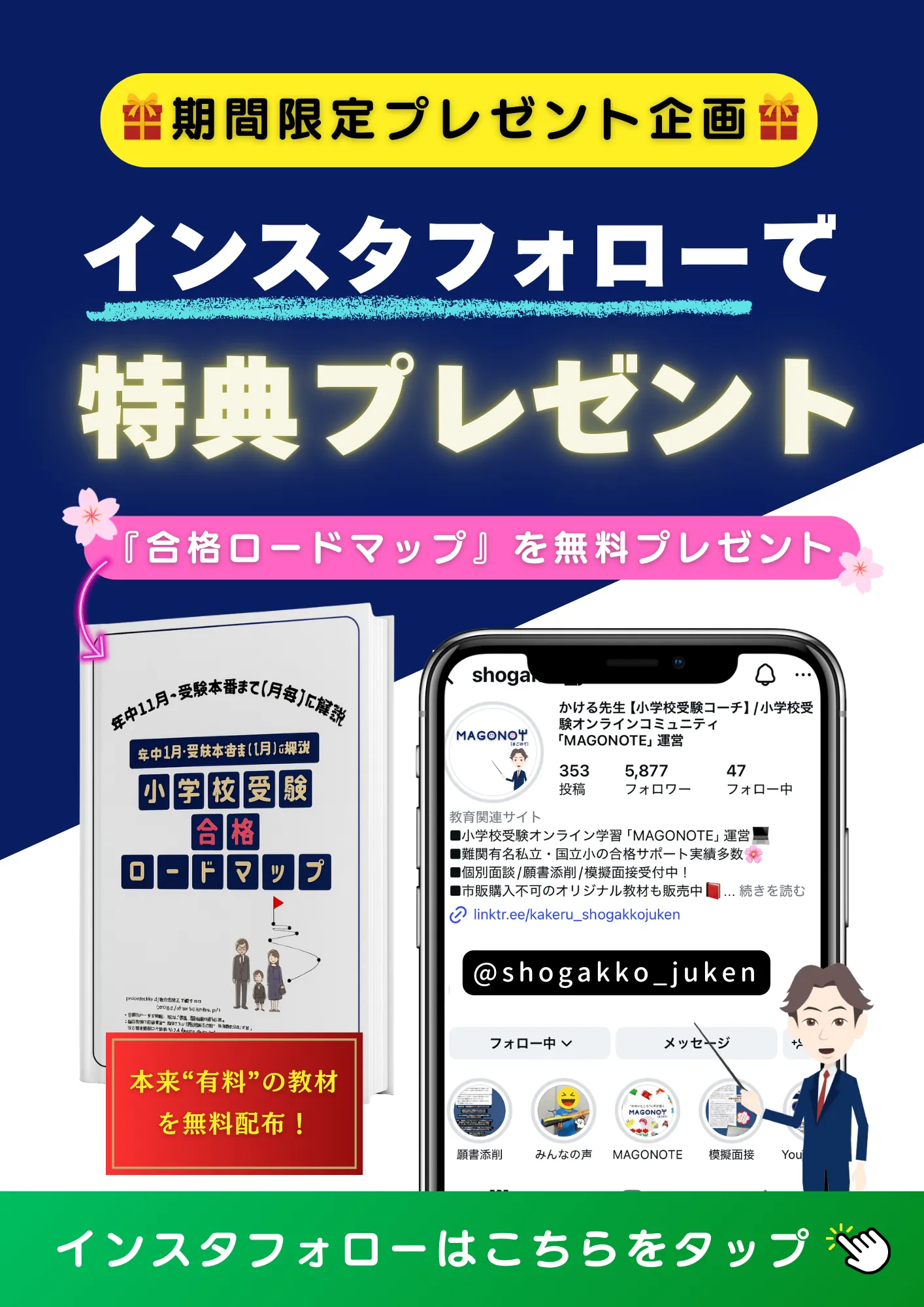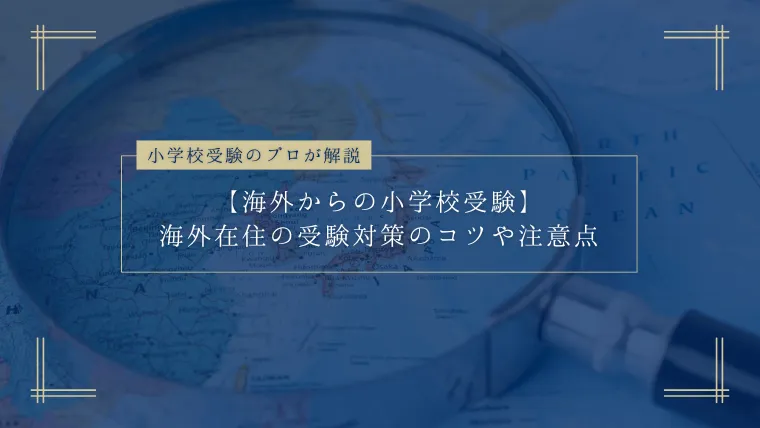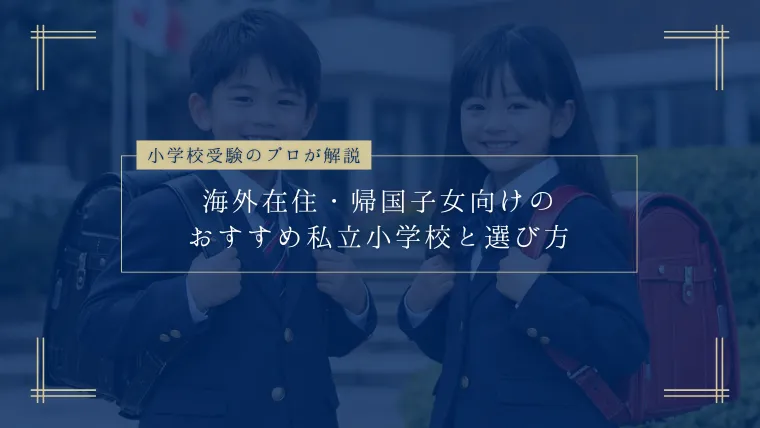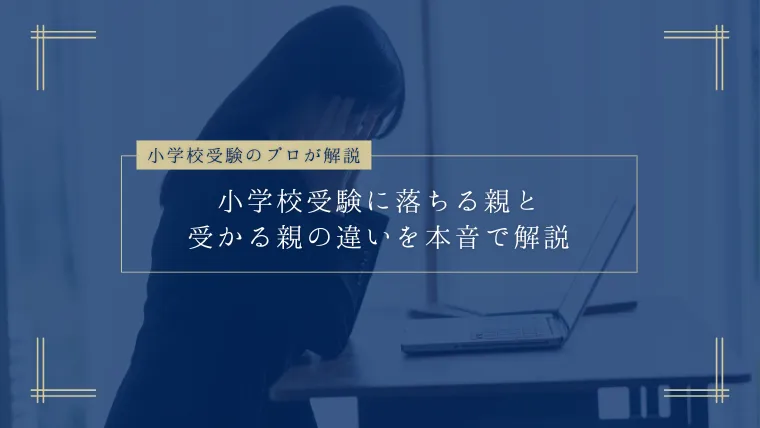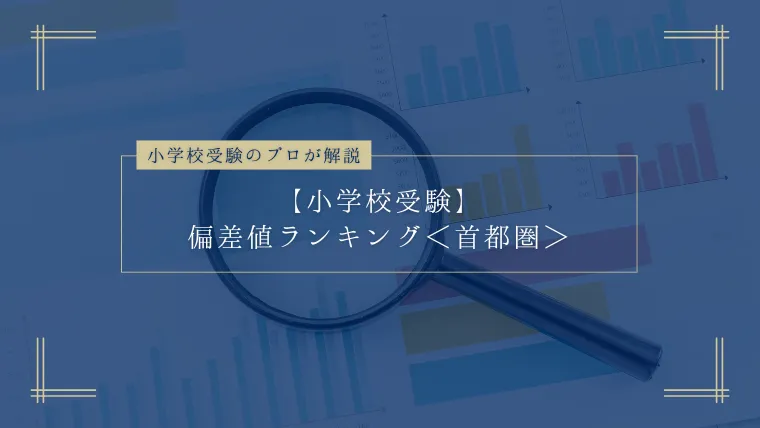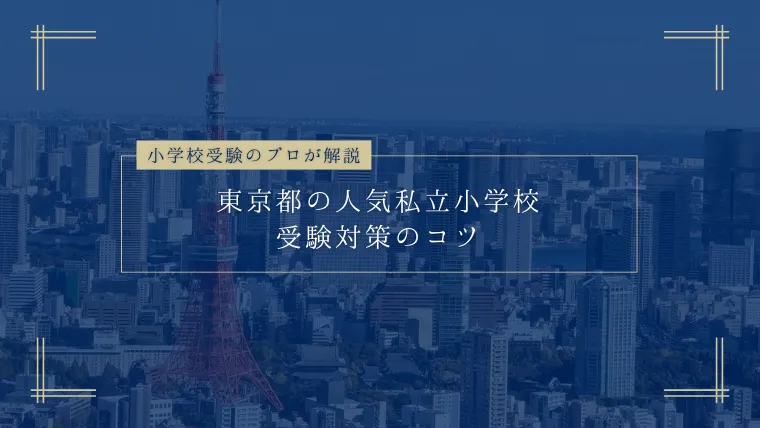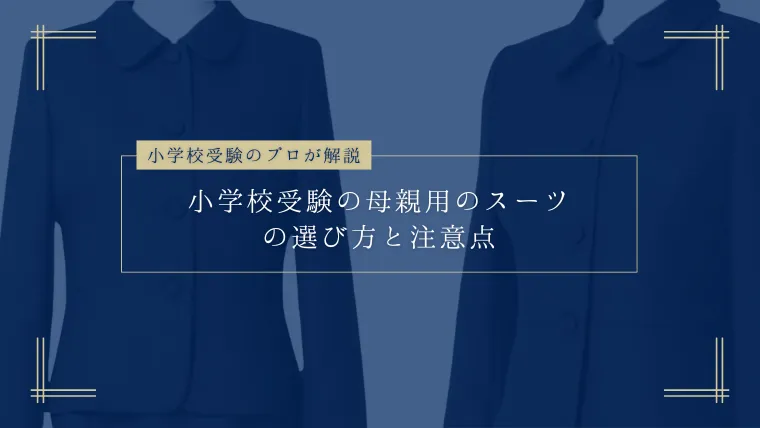小学校受験の縁故の実態とフリー家庭が意識すべきこと【プロが解説】
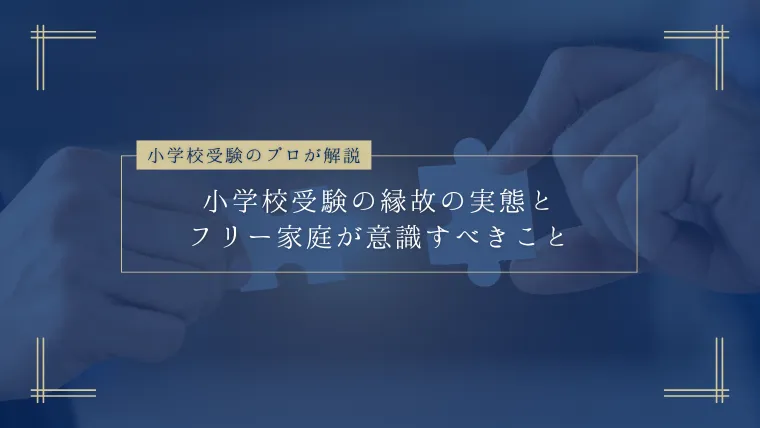
こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。
今回は小学校受験における「縁故」の実態とフリー家庭の心構えについて詳しく解説していきますね!
小学校受験を目指す上で「縁故(コネ)」という言葉を耳にすることが多いかと思います。
特に受験を控えたご家庭の中には、縁故の噂や都市伝説のような話を聞いて、
「いくら努力しても受からないのではないか」
「受験対策に意味があるのだろうか」
と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
縁故が試験にどの程度影響するのか、そして縁故やコネがないフリー家庭はどうしたらいいのか気になってしまうご家庭も多いと思います。
そのお気持ちは痛いほどわかります。
そこで今回は、これまで多くのご家庭をサポートしてきた経験や、実際に合格されたご家庭からの情報をもとに、小学校受験における縁故の実態について詳しく解説していきたいと思います。
このページは8,000字超とボリューミーな内容になっているので、何度も読み返せるように必ずブックマークをしておきましょう!
そもそも小学校受験における「縁故」とは何を指すのでしょうか?一般的には、以下のようなケースが縁故とみなされます。
・親がその学校の卒業生の場合
・兄弟姉妹が在籍または卒業生の場合
・祖父母が卒業生の場合
・関係者に身上書を渡した場合
よく「二親等までが有利」と言われますが、実際には明確な線引きがあるわけではありません。
ただし、祖父母が卒業生の場合は、学校によっては一定の縁故として扱われることもあるようです。
このような縁故がある場合、小学校受験において多少の優遇を受けることがあると言われています。
次に私立小学校受験において縁故が有利に働く理由について解説していきますね!
私立小学校、特に伝統校では縁故が有利に働くと言われています。
それにはしっかりとした理由があります。
また、その理由を知ることで、フリーで受験する場合にどんなことを意識して対策すべきかが見えてきます。
そこで以下では、私立小学校受験で縁故が有利に働く理由を解説します。
フリー枠を狙っているご家庭は、以下の内容をしっかりと押さえておくようにしましょう。
私立小学校では、家庭と学校の教育方針が一致していることが重要視されます。
特に、親が卒業生の場合、その学校の理念や教育方針を深く理解しているため、学校側も安心して迎え入れることができます。
・学校の教育方針に対する理解が深く、価値観が一致しやすい
・学校のルールや文化に慣れているため、トラブルが起こりにくい
・在学中や卒業後も、学校との良好な関係を築きやすい
近年、私立小学校では家庭の教育観と学校の方針が一致しないことによるトラブルが増えています。
このような事態を防ぐためにも私立小では面接が行われることが多いのですが、どの家庭もきっちり対策してきているためその場面では学校の理念に共感しているように見えます。
ただ、実情としては入学後に「思っていた教育と違う」と感じ、不満やクレームを入れてくる保護者も一定数いるとのことです。
こういった背景もあり、学校としてはミスマッチを避けるためにも、本当に理解してくれているという保証のあるご家庭を優遇する傾向があるのです。
また、兄弟姉妹がすでに在学している家庭も同様です。
すでに子どもが通っている場合、学校側もすでにその保護者の教育観や協力姿勢を把握しているため、安心して受け入れることができるのでしょう。
小学校受験における兄弟枠については以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はこちらもチェックしてみてくださいね。
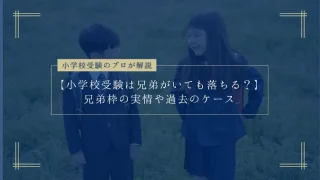
私立小学校の運営において、寄附金は教育環境の充実や施設の維持・改善に欠かせない重要な財源となっています。
特に、特色ある教育活動や新たな設備投資を行う際、寄附金による支援が大きな役割を果たすことも少なくありません。
こうした背景から、過去に多額の寄附を行った家庭や、長年にわたり継続的に支援を続けている家庭は、学校にとって非常に貴重な存在とされています。
つまり、寄附という形で学校の発展に貢献した家庭に対して一定の配慮を示すことがあるということです。
もちろん、寄附金の有無が合否を直接左右するわけではありません。
ですが、学校の理念に共感し、教育環境の向上に積極的に関与してきた姿勢は、学校に評価される要素の一つとなるでしょう。
ちなみに、数百万円規模の寄付金では、有利に働くケースはほとんどないと言われています。
特に長い歴史を持つ伝統校では、学校の文化や教育理念を受け継ぐことが大切にされています。
そのため、代々通っている家庭や、卒業生の子どもが入学することで、教育方針の一貫性や校風の維持を図ることがあります。
こうした縁故のある家庭は、学校の価値観をよく理解しており、在校生や保護者のコミュニティとの結びつきが強いため、学校側にとっても安定した教育環境を築く要素の一つとされています。
では、フリー枠の需要はないのかというと、決してそんなことはありません。
なぜなら、伝統を守る一方で、学校のさらなる発展のためには「新しい風」を取り入れることも必要だからです。
どれほど伝統のある学校でも、時代の変化に応じた価値観や新たな才能を持つ子どもを迎え入れることで、学校全体の活気や多様性が生まれ、教育の質がより向上すると考えられています。
そのため、縁故のない「フリー家庭」であってもチャンスはあります。
そのためには学校が求める価値観や教育理念に共感するとともに、どうしたら先生方に「新しい風」としての期待を持ってもらえるかを考えることが大切になります。
近年の小学校受験では、評価される子どもに少しずつ変化が見られてきています。
昨年度の小学校受験でご縁をいただいたお子様に共通して見られた特徴などについては、私が運営する小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」にて詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

先ほどお伝えしたように、縁故がない家庭でも、私立小学校への合格を目指すことは十分可能です。
たしかに縁故がある家庭に比べるとハードルが高い部分もありますが、それを理解した上でしっかりと準備することでご縁をいただける可能性はグンと上がります。
以下では、縁故がないご家庭が意識すべきポイントを整理しながら解説していきます。
受験対策だけでなく、願書作成や面接対策でも重要なことなので、今日から実践するようにしてくださいね!
縁故が有利に働く理由の一つに「学校への理解度」が関係しているとお伝えしました。
私立小学校はそれぞれ独自の教育理念や方針を持っており、縁故がない家庭が合格を目指すためには、まずその学校の求める人物像や価値観を深く理解し、それに共感していることを願書や面接を通してアピールすることが大切です。
そのためには、学校の公式HPやパンフレットだけでなく、説明会や卒業生のお話などを通じて情報を集め、学校の教育理念や特色、求める生徒像を把握することが求められます。
また、学校行事や公開授業にも積極的に参加し、実際の雰囲気を体感することで、より具体的な理解を深めることができます。
さらに、可能であれば個別相談会やお教室の座談会などを通して学校関係者や卒業生と直接話し、学校の教育の実際について詳しく知るとともに、接点を作ることも有益です。
こうした情報収集をもとに、願書や面接では「なぜこの学校でなければならないのか」を明確に伝えられるように準備することが大切です。
単に「評判が良いから」「通いやすいから」「中高大までエスカレーター式で進学できるから」ではなく、家庭の教育方針と学校の理念がどのように合致しているのかを具体的に説明できるよう整理し、学校にとって魅力的な家庭であることを伝える必要があります。
縁故がある家庭の場合、親が卒業生であることで自然と学校の文化や理念を理解しているケースが多いですが、縁故がない家庭はそれ以上に意識的に学び、説得力のある言葉でアピールすることが求められます。
私立小学校は、入学後に学校の方針と合わずトラブルを起こす家庭を避けたいと考えているため、「この家庭なら安心して受け入れられる」と思わせることが重要です。
そのためには、まず家庭の教育方針を明確にし、どのような価値観を大切にしながら子どもを育てているのかを整理することが必要です。
例えば、子ども同士の協力を重視する校風の学校を志望する場合、日頃から協調性を育む子育てを実践し、その具体的なエピソードを面接や願書で伝えるとよいでしょう。
他にも、ミッションスクールを志望する場合、日常生活の中で感謝の心を育む習慣を意識し、道徳心を養う機会を設けていることをアピールすることで、学校との相性を間接的にアピールできます。
こうした姿勢を具体的に示すことで、縁故がない家庭でも学校の求める人物像に合うご家庭であることを伝えられるため、ご縁をいただける可能性を高めることができます。
私立小学校の試験では、子どもの考査だけでなく願書や面接の内容も合否に大きく影響を与えると言われています。
特に縁故がない家庭の場合、これらの内容をしっかりと準備したうえで、「この学校でぜひ学びたい」という熱意を具体的に伝えることが重要です。
そのためには、家庭の教育方針と学校の理念がどのように一致しているのかを明確に示し、単に学校の名声に惹かれたのではなく、本当にその学校の教育に魅力を感じていることが伝わるような内容にすることが求められます。
願書では、学校の教育理念と家庭の教育方針の共通点を具体的に記述し、なぜこの学校を志望するのかを明確にすることが大切です。
面接では、家庭の雰囲気の良さや積極的な姿勢を伝えることがポイントになります。
特に、学校と家庭が協力して子どもを育てていく姿勢を示し、家庭としてどのように教育に取り組んでいるかを伝えることが重要です。
また、保護者面接では、夫婦間の連携や家庭での教育環境についても問われるため、事前に話し合い、一貫性のある回答ができるように準備しておく必要もあります。
面接や願書は、先ほどお伝えした学校との相性を示す大きなチャンスです。
そのため、縁故がない場合は、願書や面接を通して、熱意と具体性をもってアピールすることがご縁の鍵になります。
熱意や具体性のある願書の書き方については以下の記事で詳しく解説しているので、以下の記事も必ずチェックしてくださいね。
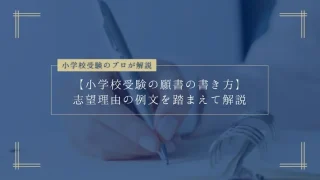
今回は、これまで多くのご家庭をサポートしてきた経験や、実際に合格されたご家庭からの情報をもとに、小学校受験における縁故の実態について解説してきました。
ここまで解説したうえでお伝えしたいのは、「フリー枠のご家庭は縁故について考えるのは今日で終わりにしましょう」ということです。
今回の記事で小学校受験における縁故についてイメージが湧いたと思います。
ただ、ご自身にそういったつながりがない場合、縁故について考えても意味がありませんし、時間がもったいないです。
縁故について悩むのであれば、その時間を1秒でも受験対策に充てたほうがご縁をいただける可能性はずっと上がります。
そのため、今回解説した内容を踏まえて、ご自身のお子さんが新しい風となるにはどうしたらいいか、どんな力を育んでいくべきかを考え、日々の受験対策に取り入れていくようにしましょう。
小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」では、今回解説した内容をさらに深堀りする形で、「縁故が試験において具体的にどれくらい影響を与えるか」「フリー枠のご家庭の子どもが意識して身につけるべきか」などについて、スライド資料を使ったプレゼン形式で解説しています。
小学校受験の一歩深い情報を知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

![小学校受験SPOT[スポット]](https://resigrit.co.jp/shogakko-juken_spot/wp-content/uploads/2024/02/shogakko-juken_spot_logo_blue.webp)