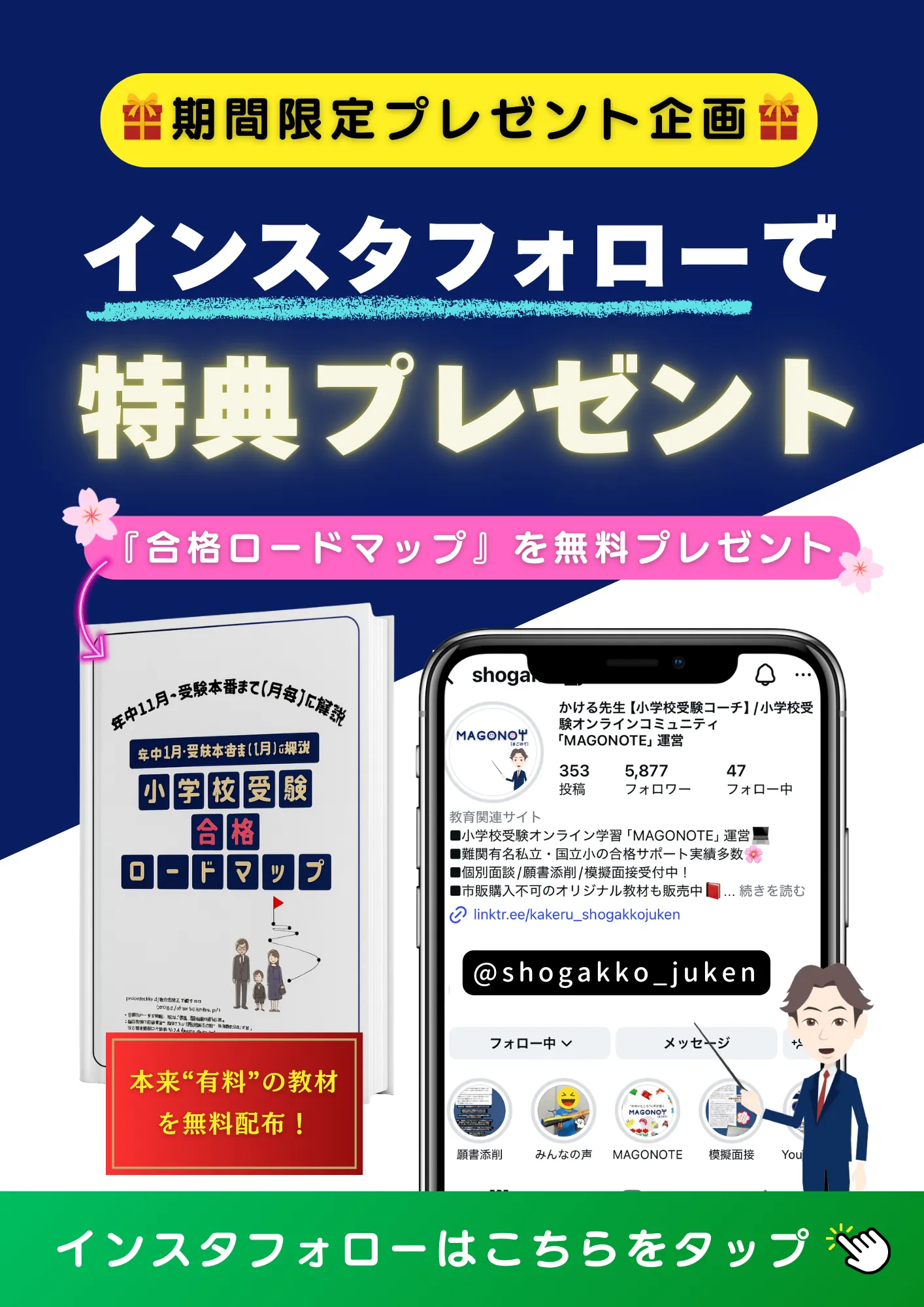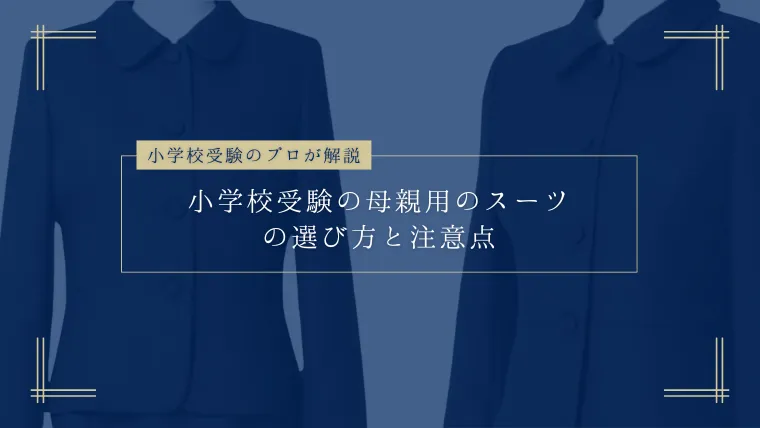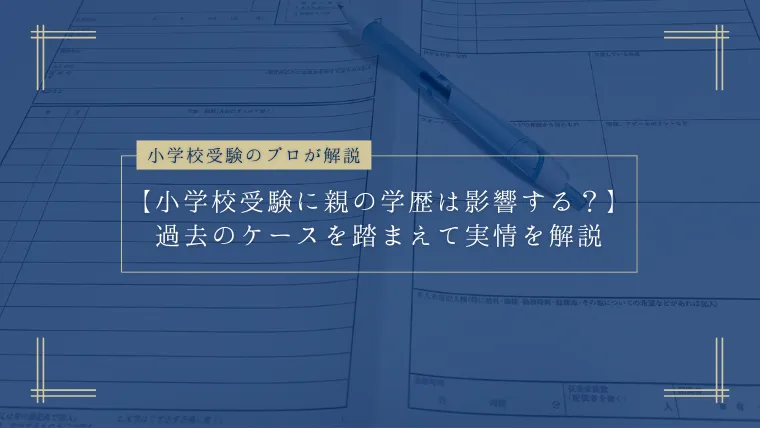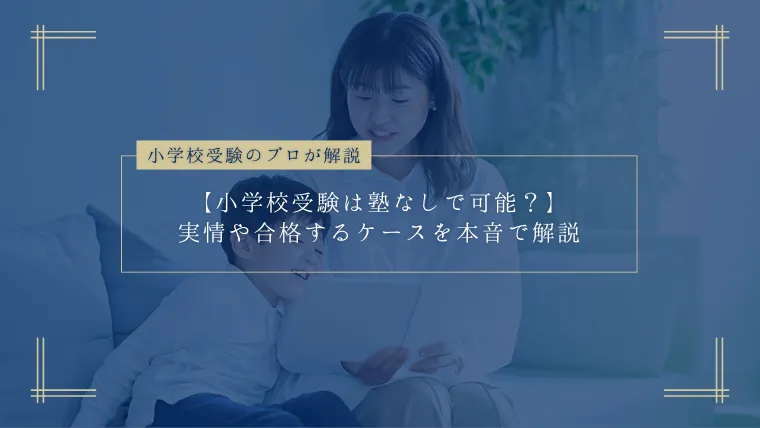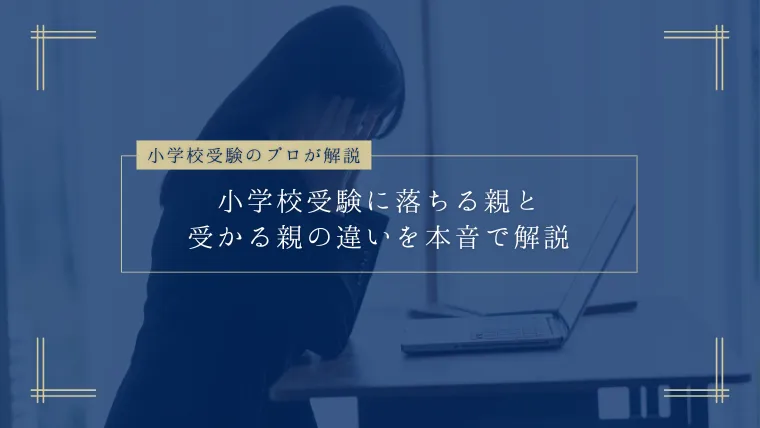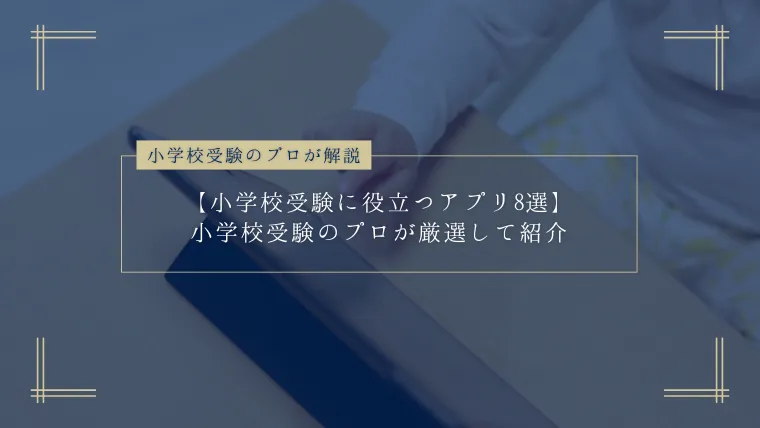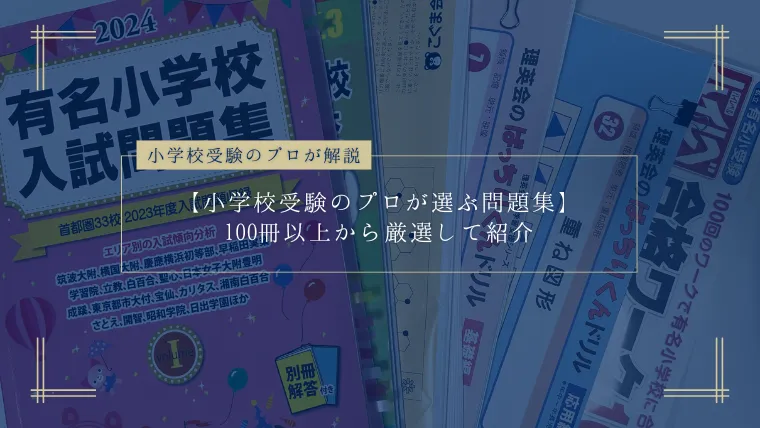【小学校受験に受かる子はわかる?】受かる子の特徴や共通点をプロが解説
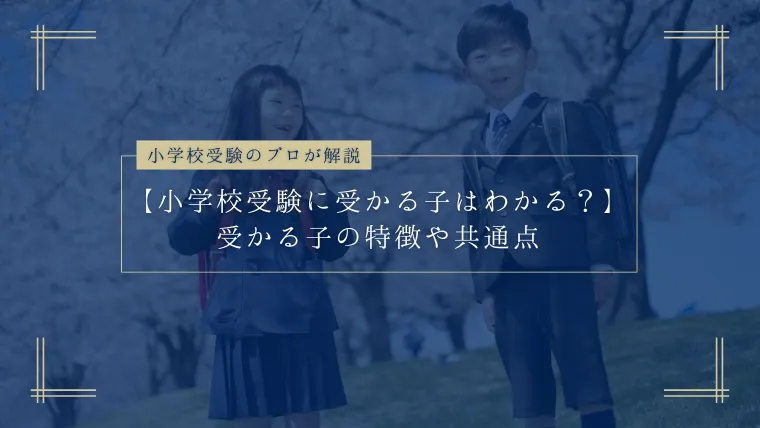
こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。
今回は小学校受験に受かる子の特徴や共通点などについて詳しく解説していきますね!
「小学校受験に受かる子って、どんな子なんだろう?」
「小学校受験に受かると言われる“光る子”“キラキラした子”って何だろう?」
「小学校受験では身体が大きい子が有利って言われるけど本当?」
そんな不安や疑問を持ちながら、日々小学校受験対策を進めているご家庭はとても多いと思います。
私自身これまで多くのご家庭をサポートさせていただく中で、受かる子にはちゃんと共通点があるということを実感してきました。
たとえば、「挨拶がきちんとできる」「集中して話を聞ける」「自分の言葉で説明ができる」…
一つひとつは特別なことではありませんが、それらを自然に、当たり前のようにできる子は、やはりご縁をいただきやすい傾向があります。
さらに、こうした表面的な能力だけでなく、生活習慣や親御さんの関わり方にも、受かる子に共通する“土台”があります。
そこで今回は、そうした小学校受験において実際にご縁をいただいている子どもたちに見られる特徴や、ご家庭での工夫・意識の違いについて、今までのサポート経験を踏まえてわかりやすく解説していきます。
そのため、ご自身のお子さんと照らし合わせながら読み進めて、日々の受験対策に活かしていきましょう。
このページは約13,000字超とかなりボリューミーな内容になっているので、何度も読み返せるように必ずブックマークをしておきましょう!

小学校受験の考査は、ペーパーだけでなく、絵画制作や運動、行動観察、口頭試問など多岐にわたります。
そのため、ご縁をいただくために必要な能力もさまざまです。
さらに、子どもによって個性や得意不得意もあるため、試験において何が強み(武器)になるかは子どもによって異なります。
その一方で、小学校受験に受かる子に共通して見られやすい能力や特徴もあるため、以下で詳しく解説していきたいと思います。
現時点でご自身のお子さんにどれくらい身についているか確認してみてくださいね!
1つ目は、基本的なご挨拶ができることです。
小学校受験に受かる子どもは、大きな声で元気に明るくご挨拶ができる子が多いです。
ご挨拶は、人間関係の最初の第一印象を決める大事な要素です。
これは大人子どもに関係なく、とても大切なことですよね。
校門で立っている先生方や試験の先生方、そういった周囲の大人に対して元気よく自分からご挨拶できるお子さんは、やっぱり先生からも気に入られやすいですし、良い評価を得やすいです。
そのため、現在お子さんがなかなか自分からご挨拶ができないという場合は、日頃から、普段の園生活やご家庭内での挨拶を大切にすることがポイントです。
また、外に出かけた時にお店の店員さんやスタッフに挨拶したり、注文したりなどするなど、自分の知らない人に対して話しかける練習を少しずつ増やすこともおすすめです。
もし現時点で難しいようであれば、親御さんが見本を見せてあげたり、最初は相手に聞こえないぐらいの小さな声でもいいので自分から言葉に出す練習をしてみてください。
2つ目は、お話や指示を聞き取れることです。
小学校受験の試験は、中学受験や高校受験、大学受験と違って、問題文を耳で聞いて理解しなければいけません。
出題方法としては、先生が口頭で読むか、録音された音声を聞くほかに、プロジェクターを使った映像での説明などもあります。
いずれにせよ、自分で文章を読むタイプではないので、一回聞き逃してしまったら、そもそも問題に答えられないんですね。
これに関してはペーパーテストだけじゃなくて、行動観察や絵画制作、口頭試問(面接)なども一緒ですね。
すべて先生の口から出た言葉をしっかりと聞いて、それを理解することが大事になります。
そのため、そもそもこの「聞き取る力」「聞く力」が前提にないと、小学校受験でご縁をいただくことはできないのです。
逆に小学校受験でご縁をいただくお子さんは、しっかりとこの聞き取る力が備わっています。
小学校受験に受かる子は、先生の指示や説明を一回で聞き取って、その通りにきちんと行動したり、動ける子が多いので、「聞き取る力」は、しっかりと早い段階から意識して鍛えていくことが大切になります。
3つ目は、説明するのが上手なことです。
先ほど、小学校受験に受かる子の特徴の一つで「聞き取る力がある」というお話をしましたが、聞き取るのが上手な子は、実は「話すのも上手」なケースが多いです。
それはなぜかというと、相手の話を聞き取れる子は、「相手が何を聞きたいのか」を汲み取れることができます。
そのため、対話している相手がどんなことを知りたいのかをしっかりと考えた上で話すことができるんですね。
逆に聞き取る力がない子は、自分が喋りたいことばっかり喋ってしまったりとか、聞かれてもいないトンチンカンなことを言ってしまうことがあります。
つまり、「説明する力」「話す力」は、「聞く力」と表裏一体ということです。
もちろん、これとは別で、説明上手な子は話したいことを言語化するための「語彙力」や「表現力」なども身についていることが多いです。
また、説明上手なお子さんの親御さんは、生まれた時から読み聞かせ習慣化していることが多いです。
そのようなお子さんは、比較的語彙力が多かったり、表現力が豊かだったりする傾向にあります。
ちなみに、小学校受験の面接では、「本は普段読みますか?」「どんな本が好きですか?」などのような質問を聞かれることも多いです、
そのため、語彙力や表現力を養いたい場合は、絵本の読み聞かせを習慣化することも大切です。
お子さんの「説明する力」は、親御さんの普段の口調や話し方も大きな影響を与えます。
そのため、同年代のお子さんと比べて語彙力や表現力が乏しいと感じたら、普段のご自身の言葉遣いや表現方法も見直してみることもポイントです。
4つ目は、集中力や落ち着きがあることです。
先ほどもお伝えしたように、小学校受験では、説明や指示を聞き取って課題に取り組まなければなりません。
そのため、先生の説明を集中力を持ったまま、落ち着いた状態で聞けるかどうかは非常に重要なのです。
学校によっては「お話の記憶」がすごい長文なところもあり、そういった学校では特に落ち着きや集中力が重視されている傾向があります。
このような力が小学校受験で大事な理由は他にもあり、「入学後にきちんと授業を聞ける子どもかどうか」というのも学校が考査を通してチェックしている大きな点のひとつです。
現に、一部の公立小学校では、若干発達障害が見られるようなグレーゾーンの子どもたちが1クラスに多数いて、その子たちが授業中に走り回ってしまったり、席を立ってしまって、そもそも授業にならないというケースがたくさんあります。
そのような状況を踏まえると、私立小学校の先生方が安定した学級運営や授業を進行するためにも、そういった「落ち着き」や「集中力」を重視している理由がご理解いただけると思います。
どんなに思考力や運動神経が優れていても、このような基本的な素地ができていないと小学校受験ではご縁をいただけない可能性があるので注意してくださいね。
4つ目は、「自分で考える力」があることです。
これは、近年の小学校受験で特に求められている力のひとつといえます。
今までは、ペーパーテストの点数が高い子や絵が上手な子、運動ができる子など、分かりやすい指標で評価していた学校も多かったと思います。
ですが、最近では行動観察や絵画制作を通して、「自分で考える力」を重視している学校が増えている印象を受けます。
その背景には、非認知能力が特に重要視されるようになったこと、AIが急速に発展したことなどが挙げられると思います。
このよう時代的変化を踏まえて、どの私立小学校も「自分で考える力」がある子を求めているのでしょう。
そのため、絵画制作課題で作品を作る時に独創的なアイディアを出せるか、自由に発想できるかが今後の小学校受験でもカギとなってくると思います。
また、このような想像力や発想力を育む際に特に重要になるのが親御さんの関わり方や声掛けです。
普段の何気ない会話でも、お子さんが自分で何か考えたり、意見を持てるように、「どう思う?」「自分だったらどうしてみる?」というように質問する習慣がある親御さんのお子さんは自由な発想力や想像力を持っているケースが多いです。
一方で、親御さんが何でもかんでも指示してしまったり、すぐに答えを教えてしまったりすると子どもの想像力や発想力は育まれません。
そのほかに、お子さんが言ってきた答えを真っ向から否定したり、自分の意見を押し付けてしまう癖がある場合も要注意です。
もし思い当たる節があるのでしたら、まずは親御さんの関わり方や声掛けから見直すようにしましょう。
5つ目は、テキパキ行動できることです。
繰り返しになりますが、小学校受験の試験では先生の指示や説明を聞き取った上で、ペーパーを解いたり、作品を作ったり、グループ課題に取り組んだりしなければなりません。
その際、「テキパキ行動できるか」もとても重要になります。
実際、難関校にご縁をいただくお子さんは、お教室の授業の中でも指示を聞いてから動くまでがとても早いです。
それに、テキパキ動ける子は、先生からの見栄えも良いです。
逆に、指示を聞いてから行動する際に一歩出遅れてしまう子は、他の子どもの中に埋もれてしまったり、よくない目立ち方をすることが多いです。
また、このようなお子さんは、普段の生活の中で何かをするときにもいつも時間がかかってしまったり、ダラダラ取り組んでいるケースが多いです。
そのため、普段の生活で次のことを考えて行動したり、メリハリをつけて動いたりする習慣を身につけることも大切です。
「あとでやる」が口癖だったり、ダラダラと生活しているお子さんは、それが小学校受験の試験でも出てしまいます。
そのため、必要に応じてタイマーを使ったり、親子でお約束ごとを決めたりして、パッと動くことを日常的に取り入れるようにしましょう。
6つ目は、楽しく一生懸命取り組めることです。
小学校受験の指示行動や行動観察では、子どもらしく取り組んでいるかもしっかりとチェックされています。
例えば、リズム運動やダンス課題は意気揚々と取り組むお子さんもいれば、恥ずかしがってしまうお子さんも多いです。
この場合、当然前者の方が良い評価を得やすいです。
また、行動観察のグループ対抗課題でも、先生方はその子たちが年齢相応の楽しみ方をしているか、そして一生懸命取り組めているかなどを見ています。
例えば、勝ち負けのあるゲームだった時に、自分のチームが勝ったら純粋に喜んで大丈夫ですし、負けてしまったら悔しがってもOKです。
なぜなら、喜んだり悔しがったりなど感情が表に出るのは、その分一生懸命やっているという証拠だからです。
逆に、それがなくて無表情の子だと、先生方も不安を覚えたりとか、心配になってしまうんですね。
そういった意味でも、試験ではあるけど、ルールやお約束の中で「子どもらしく楽しむ」ことができるかは重要なのです。
ただ、ルールを破ったりとか、負けチームを変に煽ったりとか、そういうような言動は当然いけません。
ですので、一定のルールの中で節度を持って楽しむことを普段の生活の中でも意識するようにしてください。
「ルールがあるからこそ楽しく遊ぶことができる」とお子さん自身が実感できるように、親御さんが関わり方や声かけを工夫することも大切です。
お家やお外で遅ぶときにも、ぜひこの点を意識してみてくださいね。
7つ目は、思いやりがあることです。
思いやりがあるとは、要は相手の気持ちを考えられること、そして必要に応じてお友達に声をかけたりとか、助けたりすることができることですね。
これはやっぱり、幼児期のお子さんには兼ね備えておいてほしい気持ちの一つだと思います。
ミッションスクールや、社会性・コミュニケーションを大事にする教育方針を掲げている学校は、特にこのような要素も重要視しているため、行動観察などを通してきちんとチェックしています、
実際にあった話としては、試験本番の際、入口で「行きたくない」と言って泣いちゃった子がいたときに「大丈夫だよ」「一緒に行こう」とかっていう風に声をかけた子がご縁をいただいたケースなどがあります。
もちろん、この行動一つで受かったわけではないでしょう。
ですが、そういった心が温まるような子どもらしい「優しさ」や「思いやり」が試験を通して先生方に伝わってご縁をいただけ可能性は大いにあります。
また、このような「思いやり」は、普段から親御さんがどのように伝え、どんな姿を示しているかもすごく重要です。
例えば、言葉で「もっと親切にしなさい」と伝えても、その子自身が「喜んだ経験」がないと、相手のためにどう行動すればよいかわからないんですよね。
そのため、もし現時点でお子さんが自分の気持ちを優先してしまいがちなら、「こういう時はこうするのもありだよね」というふうに言葉で伝えるだけでなく、親御さんがそれを実践して、お子さん自身が「こうしてもらえるとこんなに嬉しいんだ」と実感できるように促すことも大切です。
8つ目は、視野が広くて柔軟性があることです。
小学校受験の行動観察において、「ご縁をいただくためにはリーダーになった方が良い」「リーダーをできると受かりやすい」というふうに言われていますが、必ずしもリーダーをやらなければいけないというわけではありません。
そもそも、考査のシステム上、リーダーになれる受験生はほんの一握りですし、学校側もリーダーばかりやりたがる子だけを受け入れてしまうと、入学後の学級運営が大変になることは理解しています。
そのため、別にリーダーになることだけにこだわる必要はありません。
ですが、行動観察において、グループ活動に「ちゃんと参加する」は大切です。
ここでの「参加」とは、他の子と一緒に協力しながらも発言したり提案すること、そして、自分なりの役割を見つけて行動することなどを意味します。
行動観察において、リーダーの子が全部一人で引っ張っていくようなグループ活動の進め方は、逆にあまり良くない印象を受けます。
そのため、誰か仕切る子がいたとしても、その中でちゃんと自分の役割を認識して行動することが大切になります。
また、相手の考えもきちんと尊重しつつ、自分の考えや意見をきちんと伝える力も必要です。
そのため、お教室の行動観察の際にずっと黙ってなかなか発言できなかったり、みんなの後ろをただついていってしまう状態なら、きちんと対策していく必要があります。
ちなみに、子どもにはそれぞれ「気質」があり、リーダータイプの子もいれば、縁の下の力持ちタイプの子もいます。
そのため、まずは、お子さんがどんな気質なのかを親御さんが見極めて、それに応じた振る舞い方を丁寧に教えていくことが大切です。
例えば、「うちの子はあんまりリーダーにはなれない気質がある」っていう子は、逆に「慎重な子」が多いんですよね。
「慎重な子」は裏を返せば、周りをよく観察できているということです。
そのため、その中で「自分がどういう風な立ち回りをしたらいいのか」、「どんなことができるか」ということにフォーカスして、日々の行動観察の練習をしてみるのもおすすめです。
周りをよく観察して状況を理解した上で臨機応変に立ち回れる柔軟性がある子は、小学校受験でもかなり強いです。
お教室の行動観察の講座で身動きが取れないお子さんは、まず家庭内でシミュレーションをしてみることをおすすめします。
お教室で取り組んだ課題を復習もかねて親子で実践してみて、「こういう時はどうする?」というふうに、具体的な振る舞い方や声掛けのヒントを教えてあげるのも効果的です。

「小学校受験で見た目は影響するか」という疑問を感じている方も多いと思います。
小学校受験の先生や経験者の中には、「小学校受験に受かる子は見れば分かる」というふうにおっしゃる方もいますよね。
これは大前提として、非常に曖昧な表現で主観による部分が大きいです。
その上で、小学校受験における「見た目」の影響についてお話しします。
実際、小学校受験するお子さんの中には性別関係なく、可愛らしい子や少し見た目が整っている子がいます。
そして、「そのような子は先生の目に留まって受かりやすいのではないか」いうふうに言われることもあります。
この点に関しては、確かに「目立つ」というメリットはあると思います。
ただこれは良くも悪くもです。
小学校受験ではさまざまな試験があるため、ただ見た目が可愛らしいから、整っているからというような理由だけでは当然受かりません。
ですが、目立つ分、そこで優れた振る舞いができれば、しっかりと注目を引きつけ、高い評価を得られる可能性はあります。
ただ、逆に振る舞いが良くなければ悪目立ちもしやすいです。
また、この「キラキラしている」とか「光る」っていうのは、決して見た目だけを言ってるわけではなく、表情や愛嬌も含まれています。
例えば、子どもたちの中には、話すときににこやかな表情を見せたり、絵画制作で大人ではなかなか思いつかない発想をする子がいます。
ほかにも、行動観察などで、リーダーになって立派に仕切っていている子や、リーダーにならなくても必要な役割を見つけて自分からテキパキ動いていたり、うまく輪に入れていないお友だちに声をかけたりなどサポート上手な子がいおます。
また、このようなお子さんたちは「光るものを持っている」「キラキラ輝いている」というふうに言われることが多いです。
この「光る子」とか「キラキラする」というのは、繰り返しになりますが、「目立つ」という意味です。
ただ、目立ち方というのは、見た目的な要素が大きい子もいれば、振る舞い的な部分が大きい子もいます。
見た目的な要素は、第一印象という点では有利に働くケースもあるかもしれませんが、それだけで受かることはありませんし、結局一番大切なのは「考査での結果」です。
実際、お教室の授業であまり目立つタイプでないお子さんでも、ご縁をいただくケースは全然あります。
そのため、志望校をよく分析したうえで、その学校がどんな子を求めているのかを考えることがまずは大切です。
そして、それとお子さんの特性を照らし合わせたうえで、どのように試験でアピールすれば良いかを考え、対策していくようにしましょう。

小学校受験に受かる子の話題でもう一つよく言われることとして「体が大きい子は受かりやすい」という話が挙げられます。
実際、小学校受験にご縁をいただくお子さんの中には、同年代の子と比べて体格がしっかりしていたり、身長が大きい子もいます。
また、これも小学校受験でよく話題に上りますが、早生まれと遅生まれによる発達の影響もあります。
早生まれの子(1月1日〜4月1日)とそうでない子を比べると、体の大きさや言語の発達など、成長の度合いに差が出やすいです。
この時期の1年は大きいですから、そういった意味でも早生まれのご家庭からすると、お教室などでも「身体が大きい子が多い」と思う方が一定数いらっしゃるかもしれません。
最近では月齢によってグループ分けを行う学校も増えてきているため、そのような配慮がある場合は、極端に心配する必要はありません。
ただ、体格がしっかりしている子は、先ほどお伝えしたように「目立ちやすい」ので、そういう意味では、良くも悪くも試験において先生方の目に留まりやすいのも事実です。
そのほかにも、運動テストで筋力や動きの安定感が良い評価につながったり、行動観察などでの振る舞い方によっては精神的に大人びているように見えたりすることもあるかもしれません。
とはいえ、体が小さかったり、早生まれのお子さんでも、きちんと対策を積み重ねて合格されるケースは多数あります。
実際、そのようなお子さんでも、有名校や難関校にご縁をいただいたケースはたくさんあります。
大切なのは、もし体格や発達面で不安がある場合でも、それを「不利」と捉えるのではなく、特性を理解したうえで適切なアプローチをすることです。
場合によっては、受験対策だけでなく、療育的な視点や発達支援の専門家と連携して準備した方が良い場合もあります。
実際、そういった努力を惜しまず、しっかりと対策を積み重ねてきたご家庭が、最終的にご縁をいただいています。
小学校受験に受かる親の特徴

ここまで小学校受験に受かるお子さんが備えている能力や特徴、共通点などについて解説してきましたが、実はその振る舞いや能力を形づくっているのはご家庭です。
つまり、受かる子の背景には「受かる親の存在がある」ということなんですね。
実際に指導をしていると、小学校受験にご縁をいただくご家庭と、そうでないご家庭とでは、親御さんの関わり方に明確な違いがあることを感じます。
たとえば、合格されるご家庭に共通して見られやすい特徴として「言葉遣いが丁寧」「日常の振る舞いが穏やかで落ち着いている」「叱るときも感情的にならず、伝え方が的確」などがあります。
一方で、なかなかご縁がつながりにくいご家庭に多い傾向としては、「塾に完全に頼りきりになってしまっている」「結果や成果ばかりを重視しすぎている」などが挙げられます。
もちろん、完璧な親御さんはいませんし、最初からすべてができている必要はありません。
ですが、こうした親御さんの姿勢や日々のちょっとした行動が、子どもの内面に大きな影響を与えているということは間違いありません。
そのため、これを読んでくださっている皆さまにも、ぜひ一度、
「ご自身が、小学校受験に必要な親の振る舞いができているか」
という視点で、見直してみていただけたらと思います。
小学校受験に受かる親とそうでない親の違いや特徴については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせて確認してみてくださいね!
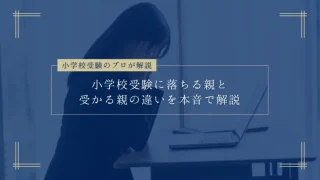

今回は、小学校受験に受かる子に見られやすい特徴や、ご家庭での工夫・意識の違いについて詳しく解説してきました。
ここまで解説してきた内容を踏まえて、今後受験対策の中でどんなことを意識して関わればよいのかを考え、実践していただけると幸いです。
また、今回の内容を踏まえたうえで、受験対策や塾選びなどについて個別で相談したい方は、随時個別面談も受付中なので、お気軽にご相談くださいね!
毎月のプロによる個別面談をご希望の方、お子さん1人でペーパーや制作や巧緻性対策できるオンライン学習環境を求めている方は、ぜひ私が運営する小学校受験コミュニティ「MAGONOTE」もチェックしてみてくださいね!

![小学校受験SPOT[スポット]](https://resigrit.co.jp/shogakko-juken_spot/wp-content/uploads/2024/02/shogakko-juken_spot_logo_blue.webp)