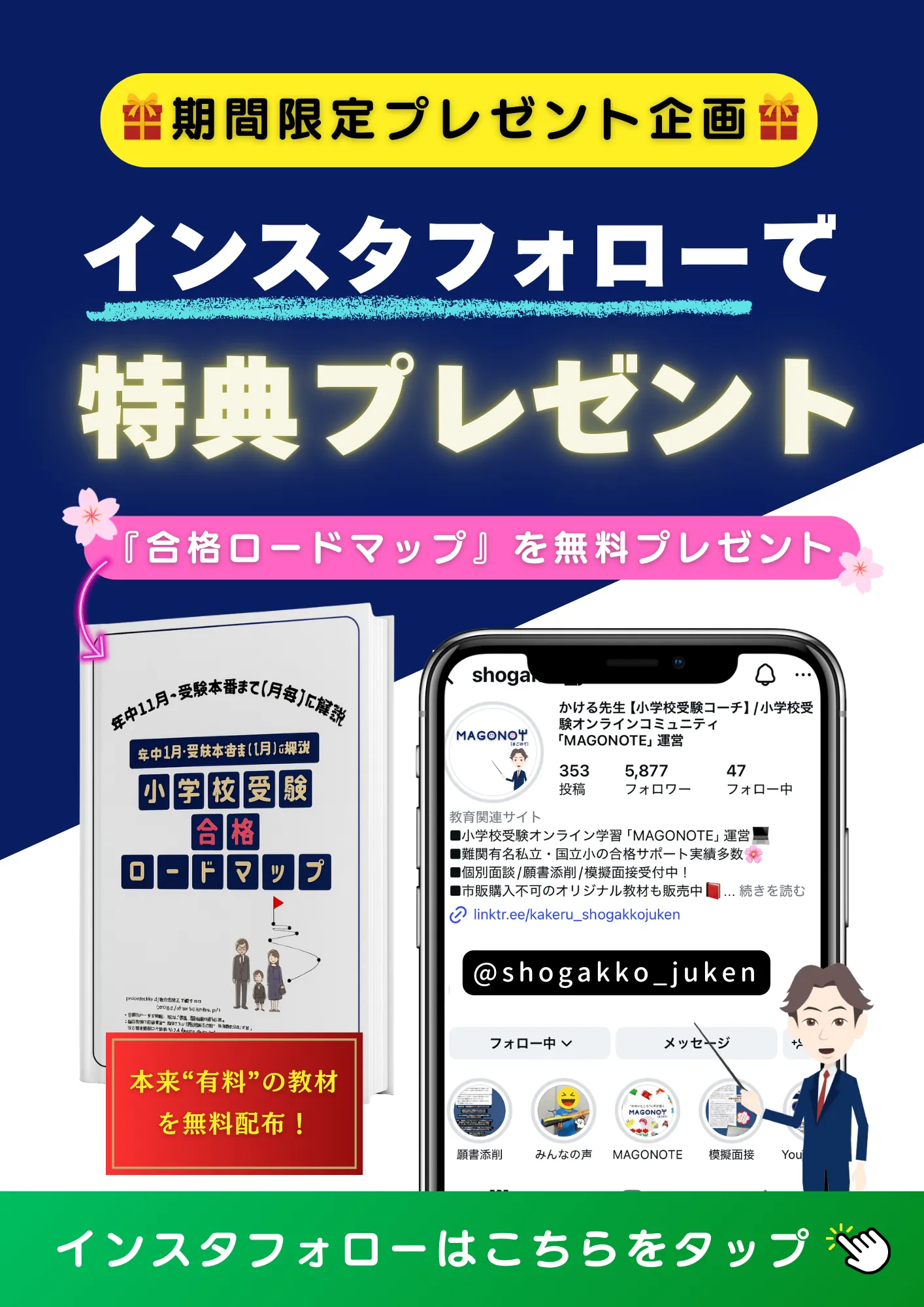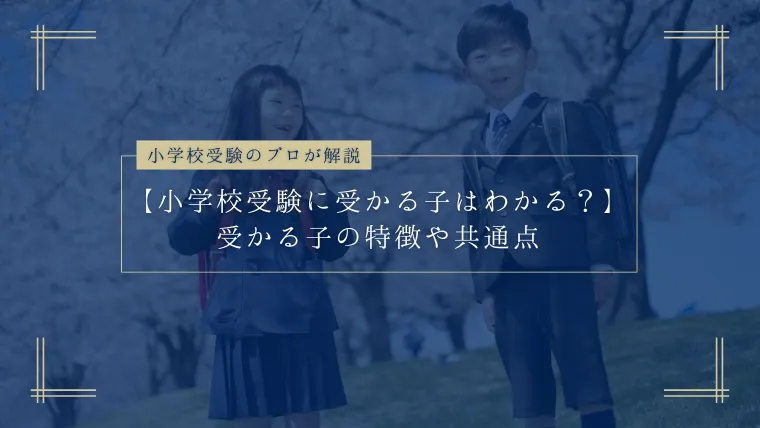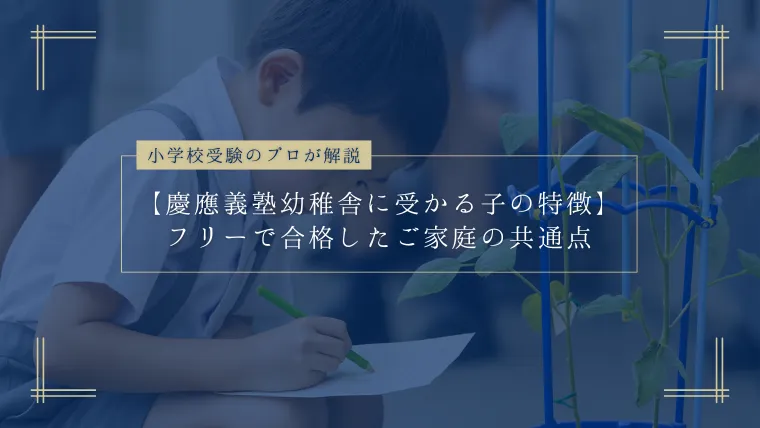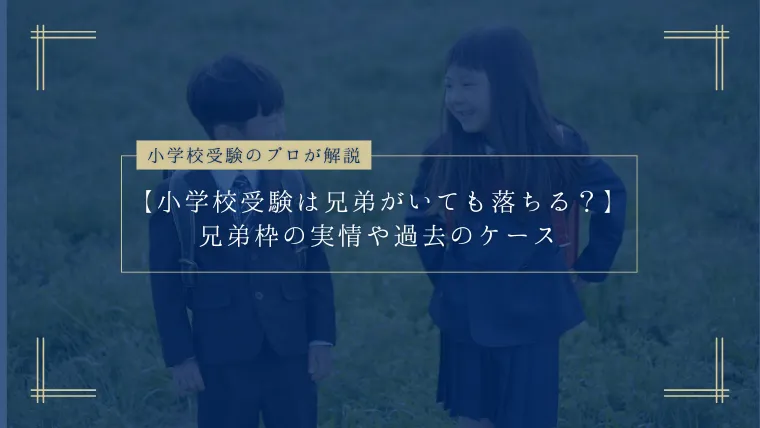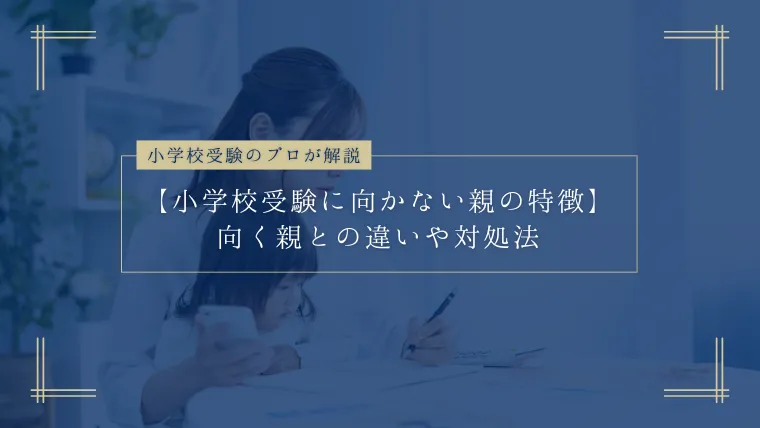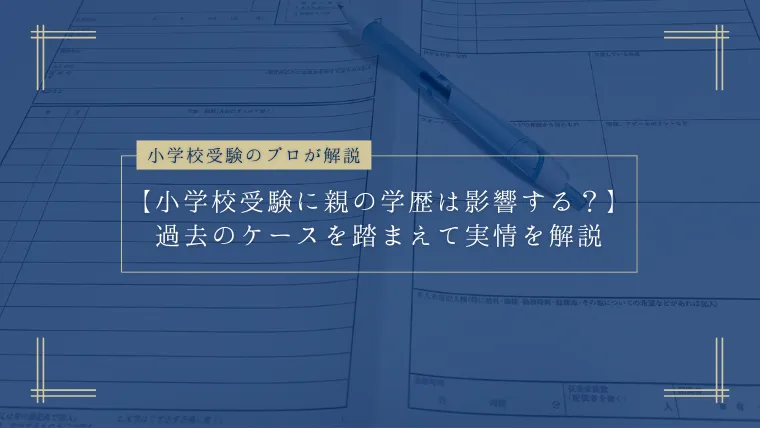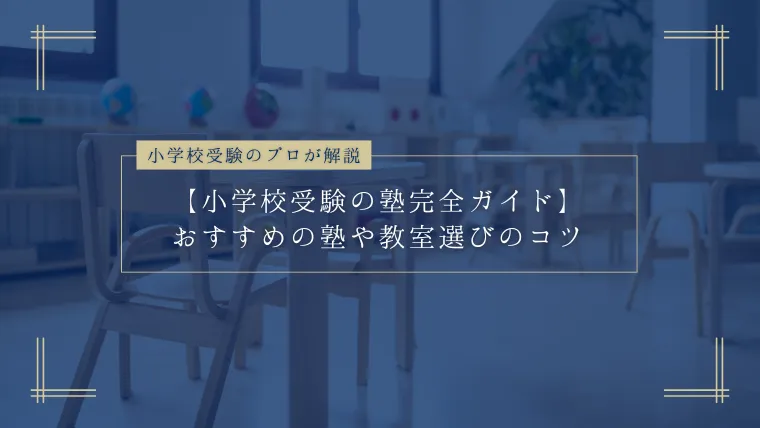小学校受験の行動観察とは?試験内容や評価基準、対策方法をプロが解説
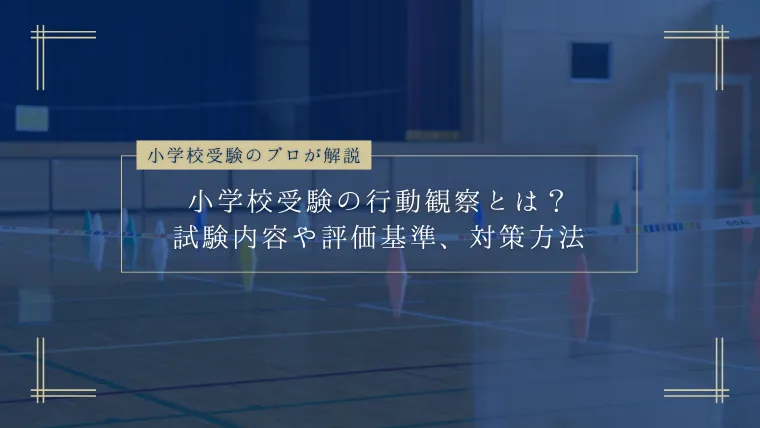
こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。
今回は小学校受験特有の考査である「行動観察」の意味や評価ポイント、家庭での対策方法などについて詳しく解説していきますね!
「小学校受験の行動観察って、どんなことをするの?」
「行動観察では、どこをチェックされているの?」
このような疑問やお悩みを抱えている親御さんも多いと思います。
小学校受験では、私立・国立を問わず、多くの学校で「行動観察」という課題が行われます。
これは、子どもを自由に遊ばせたり、他の受験生と一緒に活動させたりして、その場での振る舞いや人との関わり方を審査するものです。
中学受験や高校受験のように、科目ごとのペーパーテストだけで判断することができない小学校受験では、こうした行動観察がとても重要な役割を担っています。
特に、近年は「考える力」や「非認知能力」などを重視する私立小学校も増えているため、特に行動観察での評価はご縁をいただくうえでも重要だと言われています。
行動観察では、指示やお話をきちんと聞けるかどうかだけでなく、お友達とどのようにコミュニケーションを取るのか、協調性や社会性などがあるかについてもチェックされています。
そのため、家庭だけでなく、普段の園生活や外遊び、お教室での授業を通して、工夫しながら対策する必要があります。
そこで今回は、行動観察の試験内容や評価ポイント、家庭での対策方法などについて、実際の課題内容を踏まえて、わかりやすく解説します。
このページは、18,000字超とボリューミーな内容になっているので、何度も読み返せるように必ずブックマークをしておきましょう!
行動観察は、小学校受験において子ども同士の関わり方や集団の中での振る舞いを確認するために行われる重要な試験です。
行動観察では、先ほどもお伝えしたように、単にお行儀や指示を聞く力だけでなく、相手の気持ちを考えて行動できるか、自分の意見を伝えられるか、場の状況に応じて行動を変えられるかなど、幅広い視点で評価されます。
これは、入学後に授業や学校行事にスムーズに適応できるかどうかを判断するためでもあります。
行動観察の試験は、ブロックやボール、ままごとセット、工作道具など、さまざまな遊具・教材などを使って、お教室や体育館で行われるのが一般的です。
このように多様な道具を用意することで、子どもの性格や得意・不得意、興味の幅が自然と現れ、先生方の評価の材料になります。
また、子どもたちの安全を確保しながらも自由度を保つため、試験会場のレイアウトや道具の配置にも工夫がなされています。
構成は、5〜10人程度の小集団をつくり、約20〜30分間の活動時間を設ける形が多く見られます。
この間に、完全に自由な遊びをさせる場合もあれば、「このブロックでお城を作りましょう」「みんなで何を描くか話し合って、一つの絵を完成させましょう」など、特定の課題を与えて取り組ませる場合もあります。
自由遊びでは自発性や協調性が、課題活動では理解力やルール遵守の姿勢などが見られ、多角的に子どもの社会性や適応力を測ることができます。
行動観察の課題内容は学校によっても違いがあるので、気になる学校や志望校の過去問を早めに確認しておくようにしましょう。
おすすめの過去問シリーズは以下の記事を参考にしてみてくださいね。
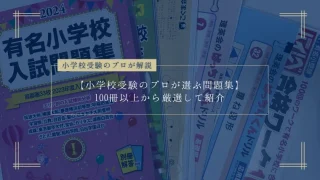
行動観察で出される課題は、学校やその年によって異なりますが、大きく分けると次の4つのタイプに分類されることが多いです。
1.自由遊び
2.共同制作・グループ遊び
3.勝敗のあるゲーム
4.真似・模倣系の課題
では、それぞれの課題タイプについて、具体例を踏まえて詳しく解説していきますね!
1つ目は「自由遊び」の課題です。
名前の通り、筆記用具や縄跳び、ブロック、フラフープなど、用意されたさまざまな道具や器具を自由に使って遊ぶ活動が行われます。
試験官は、その遊びの中で子どもがどのように行動し、周囲の子どもたちとどのような関係を築くのかを注意深く観察しています。
まず評価のポイントとなるのは、「他の子どもとの関わり方」です。
例えば、自分から「一緒に遊ぼう」と声をかけられる積極性があるか、相手から誘われたときに快く「いいよ」と応じられる柔軟性があるかは大きな判断材料になります。
ここで重要なのは、必ずしもリーダーシップを発揮する必要はなく、相手の提案を受け入れる姿勢や協調性も同じくらい高く評価されるという点です。
次に見られるのは、「集団の中での位置づけ」です。
極端に孤立していないか、逆に一方的に仕切りすぎていないかなど、集団のバランスの中で自然に振る舞えているかが問われます。
孤立している場合は、周囲に溶け込む工夫や柔軟な対応力が不足していると見なされる可能性があります。
さらに、「遊びの進め方と配慮」も重要です。
他の子どもの遊びを邪魔したり、道具を独り占めしたり、嫌がることを繰り返すとマイナス評価となります。
一方で、使いたい道具がバッティングしたときに譲り合いができる、順番を待てる、困っている子に道具を貸すなどの行動は高く評価されます。
試験官は、こうしたやり取りを通じて、相手の気持ちを理解する力や思いやりの姿勢が自然に発揮されているかを見極めています。
「自由遊び」の課題は、一見すると単なる遊びの時間のように見えますが、実際には子どもの社会性や協調性、感情をコントロールする力、他者理解力が複合的に評価される、非常に重要な課題となっています。
2つ目は、「共同制作」や「グループ遊び」の課題です。
この課題では、5〜6人程度の小さなチームを作り、特定のテーマや課題に協力して取り組みます。
例えば、指定されたテーマに沿って模造紙いっぱいに1つの大きな絵を描く、紙コップを使ってお城を作る、積み木を組み合わせてできるだけ高いタワーを作るなど、創造性と協力性の両方が求められる活動が行われます。
試験官がまず注目するのは、「協力的な姿勢」です。
チームで取り組む以上、1人だけが勝手に作業を進めたり、自分のアイデアだけを押し通したりするのではなく、他のメンバーと話し合いながら進められるかが重要です。
逆に、遠慮しすぎてまったく発言できない場合も、自発性や主体性が不足していると見られる可能性があります。
そのため、一緒に作品を完成させていく中で、互いに役割を分担したり、協力し合う姿勢を見せられるかどうかが重要になります。
また、「意見交換の質」も評価のポイントです。
自分の意見を相手にわかりやすく伝えられるかだけでなく、相手の意見を途中で否定せず最後まで聞けるか、異なる意見が出たときに妥協点を見つけられるかが重視されます。
例えば、「じゃあ半分は〇〇くんの案で、残りは私の案にしよう」など、折衷案を提案できる姿勢は高評価につながります。
さらに、「場の空気を読む力」も問われます。
発言ばかりして他の子の話を遮っていないか、困っている子にさりげなく手を差し伸べられるか、意見がまとまらないときに話を整理できるかなど、グループ全体の進行に貢献できる行動が評価されます。
この課題は、単なる共同作業ではなく、リーダーシップ・フォロワーシップ、傾聴力、調整力といった、将来の学校生活で必ず必要になる集団行動スキルを多面的に測るためのものでもあります。
3つ目は、「勝敗のあるゲーム」の課題です。
この課題では、単純なルールで短時間に結果が出る遊びが多く取り入れられます。
代表的な例としては、「じゃんけんゲーム」「玉入れ」「鬼ごっこ」「椅子取りゲーム」などがあります。
いずれも、子どもが夢中になって取り組める一方で、勝ち負けがはっきりとつくため、感情のコントロールやお友達との関わり方を観察しやすいという特徴があります。
試験官がまず注目するのは、「勝ったときの態度」と「負けたときの態度」です。
勝ったときに必要以上に相手をからかったり、威張った態度をとったりしていないか、また負けたときに泣き出したりふてくされたりして、その後の活動に支障をきたしていないかが重要なチェックポイントです。
理想的なのは、勝っても謙虚に喜び、負けても気持ちを切り替えてすぐに次の活動に参加できる姿勢です。
次に、「ルール遵守の姿勢」も評価されます。
ゲームの途中でズルをしたり、自分の都合でルールを変えたりする行動はマイナス評価につながります。
一方で、ルールをきちんと守り、他の子が間違えたときにも頭ごなしに責めず、やさしく教えてあげられる態度は高く評価されます。
さらに、「仲間との関わり方」も重要です。
チーム戦であれば、仲間を応援したり、失敗してしまった子を励ましたりできるかどうかが見られます。
こうした場面では、勝ち負け以上に協力や思いやりといった社会性が問われます。
この「勝敗のあるゲーム」の課題は、感情をコントロールする力や社会性、スポーツマンシップを総合的に評価するものでもあります。
入学後の学校生活では、運動会や競技、日常の遊びの中で勝ち負けがつく場面は多くあります。
そのときに、適切に感情を表現し、切り替えて行動できるかどうかは、クラス全体の雰囲気や人間関係にも大きく影響するため、この課題は学校側にとっても非常に重要な観察ポイントとなります。
4つ目は、「真似・模倣系」の課題です。
この課題では、試験官が実際に踊りの動作をしてみせたり、特定のポーズを取ったり、簡単な振り付けを披露したりし、それを子どもがその場で真似することを求められます。
動作は単純なものだけでなく、複数のステップが連続するパターンや、動きと同時に声を出すパターンなど、集中力と観察力を必要とするものも多くあります。
また、学校によってはより難易度を上げ、自分で想像して動くように指示するケースもあります。
こうした課題では、動きを正確に再現するだけでなく、声の大きさや抑揚、表情の豊かさ、感情の込め方まで観察されるため、子どもにとってはかなり挑戦的な内容になります。
試験官が注目するのは、「模倣の正確さ」だけではありません。
多少間違えても構わないので、恥ずかしがらずに堂々と取り組めるか、最後まで集中して真面目にやりきれるかといった「課題に向き合う姿勢」が重視されます。
例えば、動作を忘れてしまった場合でも、途中でやめてしまうのではなく、笑顔で続ける、周囲の子の動きを見て合わせるなど、前向きに対処する姿勢は高く評価されます。
さらに、この課題では「観察力」や「記憶力」、「指示理解力」も同時にチェックされます。
試験官が見せた動きを正しく記憶し、短時間で再現できるかはもちろん、動きの順序や細かなニュアンスまで意識できているかがポイントです。
これらは、授業での先生の指示理解や、日常生活での柔軟な対応力とも直結します。
このタイプの課題は、家庭でも練習しやすいので、ぜひ親子で楽しく取り組んでみてくださいね!
私立・国立を問わず、「行動観察がない学校はない」と言われるほど、行動観察は小学校受験で欠かせない重要な課題です。
その理由は、行動観察によって、基本的な挨拶ができるか、先生の指示をしっかり聞けるかといった日常的な所作から子ども同士のコミュニケーションや協調性などまで観察できるからです。
評価されるのは課題に取り組んでいる間だけでではなく、試験の始まりから終わりまでの一連の行動や態度すべてが審査の対象となります。
そのため、課題自体は問題なくこなせていても、立ち居振る舞いや態度が原因で合格を逃してしまうケースも珍しくありません。
だからこそ、行動観察で何が評価されるのかを事前に理解しておくことが、とても大切です。
そこで以下では、行動観察で先生方が特にチェックしているポイントを5つに絞ってご紹介します。
- 基本的な礼儀・態度
- 聞く姿勢と集中力
- 思いやりや協調性
- コミュニケーション力
- 創造力や持続性
それぞれどんなポイントが評価されやすのかについて、具体的に解説していきますね。
行動観察で最初に見られるのは、基本的な礼儀や態度です。
これは「課題の出来」以前に、集団生活を送るための土台となる部分です。
先生に対しては「おはようございます」「よろしくお願いします」「ありがとうございます」「ごめんなさい」「さようなら」、子ども同士でも「おはよう」「よろしくね」「ありがとう」「ごめんね」といった言葉が自然に出るかどうかがポイントです。
また、挨拶はただ言えばよいわけではありません。
声の大きさ、表情、タイミングも含めて見られています。
明るい声で相手の目を見て、気持ちを込めて挨拶できると印象がぐっと良くなります。
さらに、呼ばれたときのお返事も重要です。
「はい」とはっきり返事をし、わからないときには「わかりません」と素直に伝えられるか。こうしたやり取りは、日常の習慣として身についているかがそのまま表れます。
親御さん自身が日頃からお手本となり、挨拶や返事を当たり前に交わす家庭環境をつくることが大切です。
行動観察では、試験官の話を静かに、落ち着いた姿勢で最後まで聞けるかも必ずチェックされます。
また、ここでは「聞く力」だけでなく、「自分の体や気持ちを落ち着かせる力」も見られています。
椅子に座る場合は背筋を伸ばし、足をそろえて床につけ、手は膝の上や机の上に置く。
床に座るときも、背中を丸めたり寝転んだりせず、安定した姿勢を保つことが求められます。
また、自分の順番が来るまでの待ち方も評価されます。
おしゃべりや立ち歩きをせずに、静かに待つことは意外と難しいですが、入学後の授業態度や行事での行動にも直結するため、先生方は厳しくチェックしています。
家庭でも、絵本の読み聞かせや簡単なゲームを通して「話を最後まで聞く」「順番を守る」練習を重ねると、本番でも自然にできるようになります。
行動観察では、仲間と協力しながら行動できるか、相手の立場に立てるかが大きな評価ポイントです。
一緒に課題を進めるときに、自分のやりたいことばかり押し通さず、相手の意見も受け入れたり譲ったりできるか。他の子の作業を邪魔せず、必要に応じて手を貸せるか。
こうした行動が自然にできると、集団の中で信頼を得られます。
また、困っている子に声をかける、使っていない道具を貸すなどの小さな思いやりも、高い評価につながります。
これは日頃から「相手がどう感じているか」を意識する習慣があるかどうかで差が出ます。
協調性や思いやりは、家庭内だけでは限界があるため、友達や異年齢の子と交流する機会をつくり、実際の関わりの中で育てていくことが効果的です。
行動観察では、リーダーシップが重要と言われますが、相手の気持ちを考えないで、自分勝手に進めてしまうと逆に悪印象を与えることになるので、気をつけてくださいね。
また、リーダーになるのが苦手な場合は、逆にリーダーの意見を尊重しながら、周りの子も上手に巻き込む「No.2」の役割を担うのも一つの戦略です。
相手とのやり取りをスムーズに進める力も、行動観察でとても重要です。
最初に解説した挨拶やお礼・謝罪はもちろん、相手を遊びに誘えるか、自分の意見をはっきり伝えられるか、相手の話を最後まで聞けるかといったことが見られます。
特に共同作業では意見がぶつかることもあります。
そのときに、相手を否定するのではなく、「じゃあこうしてみよう」と提案したり、お互いが納得できる折衷案を出せるかどうかは大きなポイントです。
また、表情や相づちで「聞いているよ」と伝えることも大切です。
そうすることで、相手は安心して話せるようになり、場の雰囲気全体も良くなります。
こうしたやり取りは、日常の親子の会話や遊びの中で「相手の話を聞く→返す」を意識して繰り返すことで自然に身についていくので、ぜひ意識してみてくださいね。
行動観察では、自分の発想を形にする力と、最後までやり遂げる力も評価されます。
例えば、限られた道具で新しい遊びや作品を考える、仲間とアイデアを出し合って課題を工夫して進めるといった行動は、創造力を示します。
同時に、うまくいかなくても投げ出さず、一定時間集中して取り組み続けられるかどうかも重要です。
これは学習姿勢や粘り強さを判断する材料になります。
家庭では、自由制作や積み木遊び、パズルなどを通して「工夫して作る→最後まで仕上げる」という流れを経験させることが有効です。
ちなみに、行動観察で創造性が求められる場合、共同制作の課題が出されることが多いです。
また、共同制作で必要な創造性を養うには、指示制作と自由制作の両方を組み合わせることが重要になります。
そのためには、「無理なく制作を続けられる環境」、そして「お子様の自由な発想を促す教材」が2つが必要です。
そのような学習コンテンツが知りたい方は、私が運営している以下の「MAGONOTE(まごのて)」というオンライン学習コミュニティもぜひご活用くださいね!
詳細は以下のページからチェックしてみてください!

小学校受験のコーチングや個別面談をしていると、
「家庭でどうやって行動観察の対策をしたらいいかわからない」
「親子やお友達と一緒にできる行動観察の練習方法を知りたい」
というようなお悩みをよくいただきます。
たしかに行動観察は、他のお友だちと協力しながら取り組む試験形式が多いため、家庭でどのように練習すればよいか迷う方も多いと思います。
しかし、だからといって家庭でまったく対策ができないわけではありません。
そこで以下では、ご家庭で実践できる行動観察対策の方法やポイントを5つご紹介します。
今日から取り組めることばかりなので、ぜひ日常生活に取り入れて、親子で実践してみてくださいね!
行動観察の試験では、友達との協力やコミュニケーション力が注目されることが多いですが、その前提として欠かせないのが 「指示を聞き取り、その通りに行動する力」 です。
いくら発言が上手でも、試験官からの指示を聞き漏らしたり、順序を間違えて行動してしまうと評価が下がってしまいます。
この「聞く力」は一朝一夕では身につかないため、日常生活の中で意識的に練習していくことが大切です。
たとえば、
「タンスの上から2段目の引き出しから靴下を取ってください」
「上から4段目の棚から〇〇を持ってきてもらえる?」
のように、場所や順序が明確になるような声かけを心がけてみましょう。
こうした練習を繰り返すことで、子どもは指示を頭の中で整理しながら動く習慣がつきます。
また、お願いをする前には 「今からお母さんが言うことをよく聞いてね」 のように、注意を引く一言を添えると効果的です。
特に子どもは遊びや別の作業に集中しているとき、指示が耳に入っていないことも多いため、聞く姿勢を整えてから話すことがポイントです。
さらに、慣れてきたら指示の内容を少し複雑にしてみましょう。
例えば、
「靴下を取ったら、そのままリビングの机の上に置いてね」
「本棚の右から3番目の本を持ってきて、お父さんに渡してね」
といったように、複数の行動を順番通りに行う練習を取り入れると、記憶力や集中力も同時に鍛えられます。
この「指示行動」の力は、行動観察試験だけでなく、ペーパー試験や制作課題、面接の場面でも必要になります。
普段の生活を通じて少しずつトレーニングし、自然にできるようにしておくことが、試験本番での大きな安心につながります。
行動観察の試験では、協調性や思いやりと同じくらい、「自分で考えて行動し、周りをまとめる力」、つまり“リーダーシップ”も評価されます。
また、これはいきなり身につくものではないため、日々の生活の中で繰り返し経験することで少しずつ育んでいく必要があります。
そこでおすすめなのが、家庭内でできる「小さなプロジェクト」をお子さん主体で進めることです。
例えば、お休みの日に「動物園に行く」という予定がある場合、まずは前日や数日前に家族会議を開き、お子さんにリーダー役を任せます。
そして、以下のような議題について話し合いましょう。
・当日は何時に起きて、何時に出発するか
・どの交通手段で行くか(電車・車・バスなど)
・動物園の中をどの順番で回るか
・お昼ご飯はどこで、何を食べるか
・おみやげを買うなら、予算はいくらにするか
そうする中で、子どもは「決める」「説明する」「周囲の意見を聞く」という経験を重ねることができます。
これが行動観察で求められるリーダーシップや主体性の土台になります。
もちろん、最初からすべてを自分で進行するのは難しいので、必要に応じて、親御さんがサポート役として関わるようにしましょう。
例えば、
「次は何を決めたらいいかな?」
「○○くん(ちゃん)は、どうしたい?」
「じゃあ、それで決まりでいいかな?」
といった問いかけを挟み、お子さんの発言や判断を引き出すようなイメージです。
さらに、計画を立てる段階だけでなく、当日もリーダーとしての役割を持たせましょう。
動物園では「次はどこに行くか」をお子さんに提案してもらったり、家族の先頭に立って案内してもらったりすると、実際に「進行・推進する力」が養われます。
このような小さなプロジェクトを日常的に積み重ねることが、行動観察試験で生きるリーダーシップと主体性を自然に育む近道になります。
そのため、特別な準備をしなくてもよいので、日々の生活の中にこうした機会を意識的に作ってあげることがポイントです。
行動観察の試験では、ただ意見を言うだけでなく、「状況を整理し、解決策を導き出す力」も求められます。
これがいわゆる「問題解決スキル」です。
たとえば、グループ活動で意見が分かれたときや、計画が思い通りに進まないとき、この力がある子は冷静に対応し、周囲をまとめることができます。
では、この力を家庭でどう育てればよいのか。
そのポイントは、親御さんがお子さんに相談することです。
大人が悩みを打ち明け、「どう思う?」と尋ねることで、お子さんは”自分の考えで人を助ける”という経験を自然と積むことができます。
例えば、
「お母さん(お父さん)、冷蔵庫がいっぱいで今日買った玉ねぎが入らないんだけど、どうしたらいいと思う?」
「明日出かける時間を午前と午後で迷っているんだけど、どっちがいいかな?」
などのような質問を投げかけると、お子さんは「お母さんやお父さんの役に立ちたい」という思いが芽生えて真剣に考えてくれます。
さらに、「理由も一緒に教えてくれる?」と付け加えると、論理的に説明する練習にもなります。
また、このような会話だけでなく、以下のような遊びの中でも問題解決スキルは鍛えられます。
・ジグソーパズルやブロック遊びで「どうやったら完成できるか」を考える
・謎解きや間違い探しで「ヒントから答えを導く」経験を積む
・ボードゲームで「勝つための作戦」を話し合う
このように、日々の生活の中で「相談」と「遊び」を組み合わせることで、お子さんは「自分で考え、選び、説明する力」をバランスよく伸ばせます。
そして、この積み重ねが、行動観察試験の場での発言や提案の質を大きく高めることにつながります。
こうした遊びは楽しみながら試行錯誤を繰り返すため、自然と柔軟な思考力が身につけることができます。
そのため、ぜひ日常生活に取り入れるようにしてくださいね!
行動観察の試験では、自分の考えや意見をわかりやすく伝える 「言語力」 が重要視されます。
特にグループ活動の場では、聞かれたことに答えるだけでなく、自分から意見を述べたり、提案したりする力が求められます。
この力を家庭で育てるのにおすすめなのが、「小さな発表会」を習慣化することです。
発表のテーマは難しいものである必要はなく、むしろ身近な内容に設定しましょう。
例えば、
「今日、保育園(幼稚園)で一番楽しかったこと」
「今日1日で新しく学んだこと」
「読んだ絵本で心に残った場面」
といったように、日替わりで簡単に話せるテーマを用意します。
できれば毎日テーマを変えることで、さまざまな話題に触れる練習になります。
発表後はまず、「最後まで話せたね」「わかりやすかったよ」など、肯定的な言葉を先にかけ、その後で「もっと声を大きくするといいね」や「順番をつけて話すともっと伝わるよ」といったフィードバックを添えてあげましょう。
褒めてから改善点を伝えることで、お子さんは自信を持ちつつ向上心を養うことができます。
また、発表会の場だけでなく、普段の会話でも「自分の考えを言葉にする」機会を増やすことが重要です。
例えば、
「今日、幼稚園(保育園)でどんな遊びをしたの?」
「○○くん(ちゃん)は、これについてどう思う?」
「今日は公園で何をして遊びたい?」
といった質問を投げかければ、日常生活の中で自然と発言や提案の場が増えます。
このように意識して会話や発表の機会を積み重ねることで、親子のコミュニケーションが深まり、それに伴って語彙力や表現力も自然に伸びていきます。
そして数ヶ月続けるうちに、行動観察のグループ活動でも自信を持って発言できるようになる子が多いです。
お教室の行動観察の授業で「なかなか発言できない…」という方は、家庭でのお子様の言葉の数を増やすように意識してみましょう。
行動観察では、グループでの活動や初めて会うお友達との対話や協力が求められます。
しかし、普段から限られた相手としか関わっていないと、いざ試験本番で初対面のお友達と話すときに緊張し、思うように動けなくなってしまうことがあります。
特に、「お父さん・お母さん」「祖父母」「保育園や幼稚園の先生」「仲の良い友達」など、決まった顔ぶれとのやり取りがほとんどというお子さんは要注意です。
なぜなら、こうした環境では未知の相手に話しかける経験がほとんど積めないからです。
この苦手意識をなくすには、初めて会う人や普段あまり話さない人と関わる機会を意識的に作ることが大切です。
たとえば、いつもとは違う公園に行き、その場で遊んでいるお友達と一緒に遊んでみたり、児童館に行って年上のお兄さん・お姉さんや年下の子と関わったり、習い事の体験会やイベントに参加して他の子と協力する経験を積んだりなどなど。
こうした場では、最初は緊張して言葉が出ないかもしれませんが、「どうやって声をかければいいか」「相手の反応にどう返せばいいか」をアドバイスして実践を重ねることで、少しずつ身についてきます。
やがて、初対面でも自然に会話や共同作業ができるようになり、行動観察の場でも積極的に動けるようになります。
大切なのは、「慣れ」を作るために日常的に場数を踏むことです。
そのため、試験直前だけではなく、普段から意識的に環境を変え、新しい人とのやり取りを経験させてあげるようにしてくださいね!
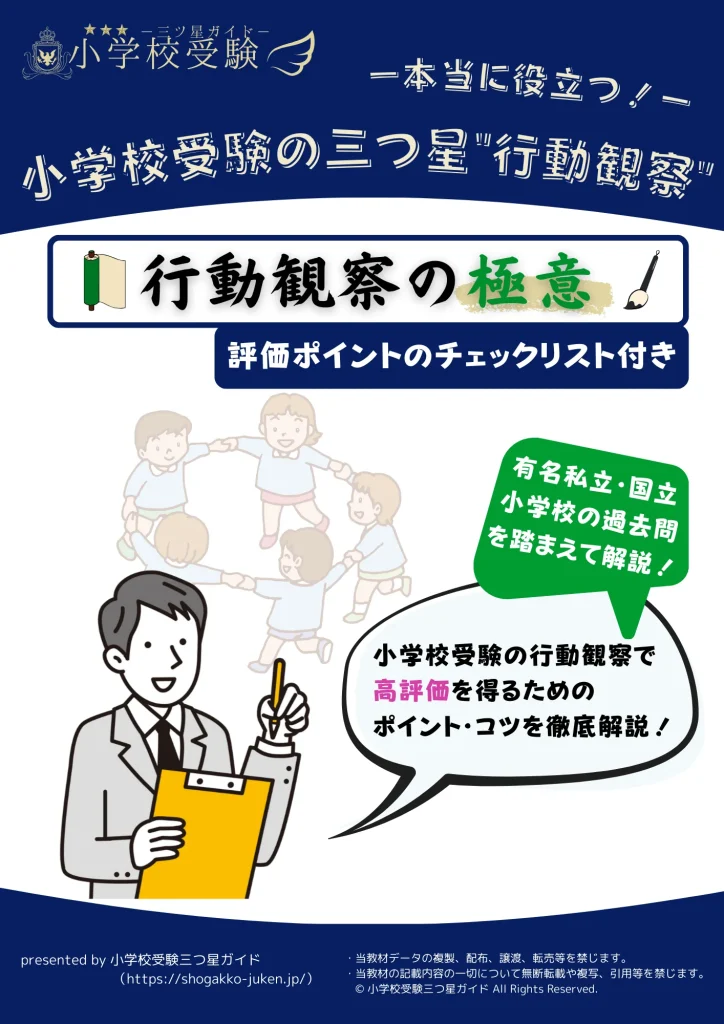
行動観察に不安を感じている方は、私のオリジナル教材『行動観察の極意』をご活用ください。
本教材では、
「ご家庭で実践できる行動観察対策の方法とポイント」
「実際の試験で出題される課題の種類や具体的な事例」
「試験官がチェックしている評価項目リスト」
など、行動観察に関するノウハウを余すことなく丁寧に解説しています。
近年、小学校受験における行動観察の重要度は年々高まっており、多くのご家庭が力を入れて対策を進めています。
こうした中で差をつけるためには、「ただ練習する」だけでなく、評価基準を理解したうえで的確な準備をすることが欠かせません。
「行動観察で何を見られているのか知りたい」
「他のご家庭に負けないテクニックを身につけたい」
「家庭でできる効果的な練習法を知りたい」
そんな方にこそ、『行動観察の極意』は役立ちます。
まずは以下のリンクからサンプルをご覧いただき、ぜひご家庭の対策にお役立てください。
今回は、小学校受験における行動観察の試験内容や評価基準、家庭での対策方法などについて、包括的に解説してきました。
行動観察について詳しく知らなかった方の中には
「結構難しいなぁ…」
「思ったより奥が深い」
と思った方も多いと思います。
しかし、行動観察は、お教室での授業だけでなく、普段の園生活や家庭での過ごし方が滲み出る試験でもあります。
そのため、今回解説したポイントを踏まえて、対策に取り組んでみてくださいね。
小学校受験の現役講師兼コーチである私が運営している小学校受験オンラインコミュニティ「MAGONOTE」では、行動観察をはじめとした受験ノウハウや制作・絵画などのオンライン教材、願書・面接対策にも役立つコンテンツが多数あるため、気になる方はこちらもぜひチェックしてみてくださいね!
![小学校受験SPOT[スポット]](https://resigrit.co.jp/shogakko-juken_spot/wp-content/uploads/2024/02/shogakko-juken_spot_logo_blue.webp)